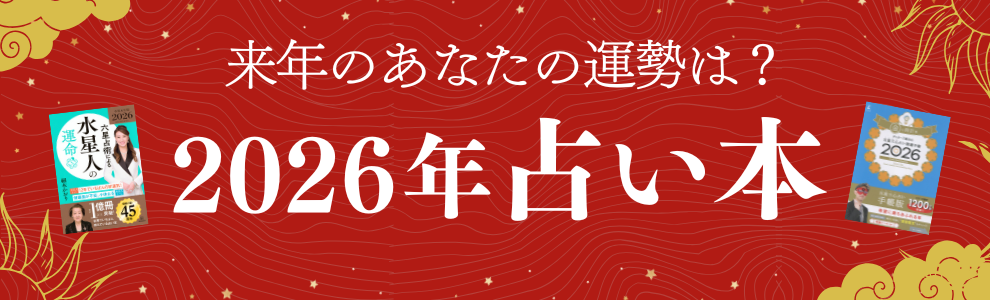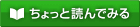[BOOKデータベースより]
陰翳とは何か。それが日本的なものだとはどういうことか。建築と小説という異なる領域の交錯する地点から、日本的なものという一九三〇年代の主題を捉えなおす。
「陰翳礼讃」を読み解く
1 タウトと日本の建築、タウトと日本の建築家(桂離宮の弁証法―ブルーノ・タウトの「第三日本」;建築における日本的なものという主題―タウトと日本の建築家たち)
2 フィクションの中の建築家(ブルーノ・タウトと日本の風土―石川淳『白描』と井上房一郎;美しい日本、戦う日本―黒澤明のシナリオの中の建築家たち)
3 建築の語り方、「日本」の語り方(喪失と発見―坂口安吾「日本文化私観」と岡本太郎;富士山という解答―丹下健三「大東亜建設忠霊神域計画」と横山大観)
4 長編小説の中の建築家(結婚と屋根―横光利一『旅愁』と建築の日本化;帝国における結婚―谷崎潤一郎『細雪』と建築家という結び)
「陰翳礼讃」を振り返る
小説家としての谷崎潤一郎の名前を超えて、ひろく、長く読まれてきた「陰翳礼讃」―― 陰翳とは何か。それが日本的なものだとはどういうことか。
「陰翳礼讃」は創元選書の表題作になったことを契機に、谷崎潤一郎という小説家の個人的な随筆から、知識階級の読む日本文化論へと進化(グレードアップ)した。「陰翳礼讃」というテキストは、「文化」を謳う一九三〇年代の知的な教養の中に位置づけられたのである。
「陰翳礼讃」は、命題として何が語られているかだけでなく、何事かを語るレトリックそれ自体を読み解くベきテキストである。「陰翳礼讃」で行われているのは、建築を文学を語るための比喩として組織すること、すなわち建築を文学の修辞とすることである。
一九三〇年代、建築界では建築における「日本的なもの」が論じられた。その議論に触発された小説家たちは、建築を媒介にしてそれぞれに思索を展開した。本書で取り上げるのは、そのような思考の痕跡の刻まれたテキストである。本書では、小説家たちが話題にする建築家や建築物、建築論を広義の比喩と見なし、その表現を同時代の文脈の中で読み解く。
谷崎潤一郎、夏目漱石、ブルーノ・タウト、岸田日出刀、堀口捨己、丹下健三、磯崎新、石川淳、黒澤明、伊東忠太、坂口安吾、岡本太郎、前川國男、横山大観、横光利一、下田菊太郎、小林秀雄……
建築と小説という異なる領域の交錯する地点から、日本的なものという主題を捉えなおすこと、本書のねらいはそこにある。本書の独自性は、建築界の議論と小説家のテキストが交錯する範囲を画定し、そこに対象を再配置する点にある。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 猫うた 千年の物語
-
価格:1,760円(本体1,600円+税)
【2024年11月発売】
- すぐ読める! 蔦屋重三郎と江戸の黄表紙
-
価格:1,870円(本体1,700円+税)
【2024年12月発売】
- 再読日本近代文学
-
価格:2,350円(本体2,136円+税)
【1995年10月発売】
- 日本の恋歌とクリスマス
-
価格:1,870円(本体1,700円+税)
【2021年12月発売】