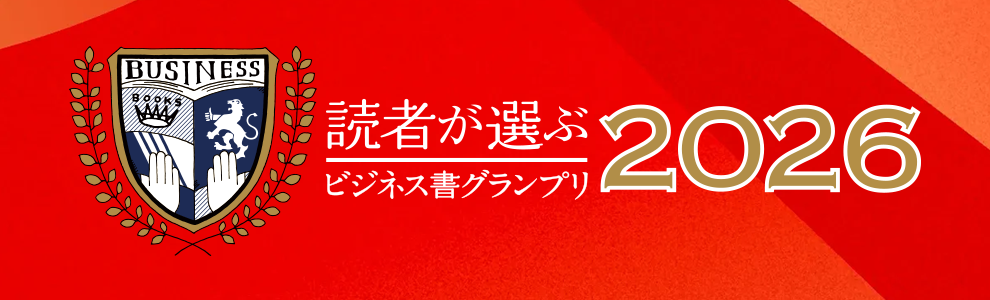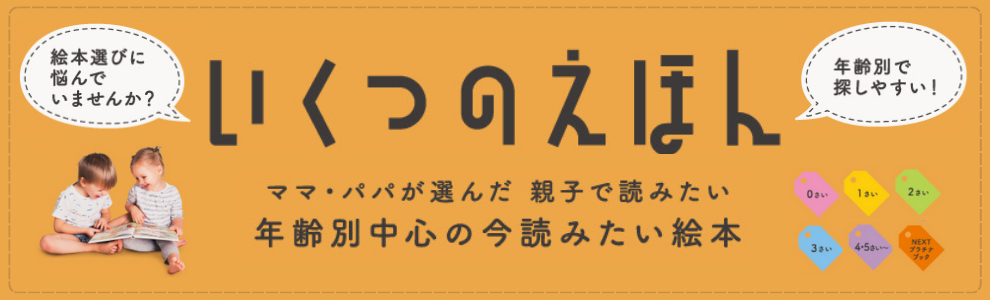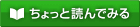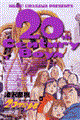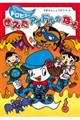[BOOKデータベースより]
戦前に健康な乳幼児を表彰する、「赤ちゃん審査会」というイベントが大阪府堺市で開催されていた―貧困者救済事業から社会事業への変遷、太平洋戦争下の一九四二年までの激動の一五年間を、「堺市赤ちゃん審査会記念写真帖」を通して定点観測する。
第1部 「産む」ことをめぐる制度の変遷と赤ちゃん審査会(赤ちゃん審査会がめざしたもの―くり返された「世界一高い乳児死亡率の防遏」という目標;「健康」「衛生」概念の普及とメディア・イベントとしての赤ちゃん審査会;産院の時代―一九二〇年代施設型出産の定着から国民医療法による制度化まで;社会事業と産師法(産婆法)制定運動)
第2部 堺市赤ちゃん審査会記念写真帖(「堺市赤ちゃん審査会記念写真帖」について;お産と育児の展覧会・乳幼児審査会記念写真帖;第二回堺市赤ちゃん審査会記念写真帖;第四回堺市赤ちゃん審査会記念写真帖;第五回堺市赤ちゃん審査会記念写真帖 ほか)
「児童愛護」はいかにして「優生思想」に結びついたのか。
戦前に健康な乳幼児を表彰する、「赤ちゃん審査会」というイベントが大阪府堺市で開催されていた――貧困者救済事業から社会事業への変遷、太平洋戦争下の1942年までの激動の15年間を、「堺市赤ちゃん審査会 記念写真帖」を通して定点観測する。
***
本書は、乳幼児保護を目的として戦前に大阪府堺市で開催された「赤ちゃん審査会」の記録写真帖の復刻、およびこのメディア・イベントの社会的背景、担い手、および意義を歴史社会学的に考察した論考の二部からなる。貴重な記録写真とそれに基づく考察を通し、日本の近代化と戦時体制への人々の動員と社会変化を理解することができるだろう。
具体的には、近代化に伴う「衛生」「健康」概念の普及活動、そして近代的な出産と育児を教育する担い手となった産婆(助産婦)の実践を通して、戦前日本における人びとがどのようにして衛生観念を身につけ日常知としていったのか、そのために国家や医師はどのような手段を用いて乳幼児死亡率の低下と人口増加を達成しようとしたのか、その媒介となった産婆の果たした役割に焦点を当て考察する。