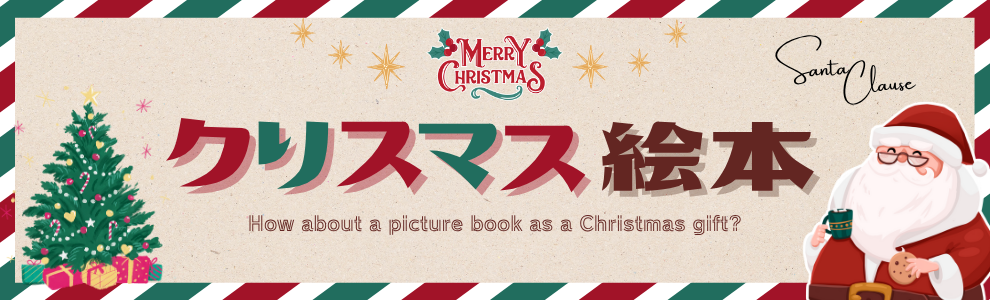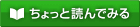[BOOKデータベースより]
犯罪をした人たちはルールを守れない?再犯を防ぐためにはコントロールしなければならない??相手を無理にでも変えようとすると、援助的なかかわりがうまくいかず相手との関係自体が崩壊することがある。そのような問題を回避するためには当事者と援助者に「共助する関係」が必要である。
第1部 導入編 「共助する関係」という提案
第2部 物語編 「共助する関係」の形成・維持の基本(本心はなかなか言えない―本人の事情に配慮し、周囲の事情に注意する;怒っている人は困っている人―正論で相手を説得しようとしない;コントロールではなくコミュニケーションを―安心・安全な空間を用意して、感情よりも内容に注目する;相手の考えや行動は、自分の期待と違っていて当然―状況を客観視してみる;他人の問題点は目につきやすい―トラブル時こそ非審判的態度を保つ;自分で決める、という経験の意味―自己決定を支援して、尊重する;言いたくないこと、言えないことは誰にでもある―秘密を守る)
第3部 発展編 「共助する関係」に役立つ知識(援助にあたっての原則;当事者を理解するための視点;援助者が自己理解を深めるためのヒント)
2011年度末に全国の各都道府県において設置が完了し事業を開始している「地域生活定着支援センター(以下、定着支援センター)」。この事業の主たる目的は、対象者を帰住先における社会福祉サービス事業者に適切につなぎ、社会資源の利用を促進することを通じて、本人の生活の安定と生活の質の向上を図ることである。
定着支援センターに期待される機能として、地域資源の開拓や個別ケースの支援のためのネットワーク形成があり、コーディネーションの役割を担い、地域にある既存の社会福祉サービス事業者が実際の支援を提供している。これに加えて、ここ数年のあいだに、被疑者・被告人段階の高齢あるいは障がいのある人に対しても、さまざまな社会資源を利用したり、福祉サービスを導入したりする試みがはじまっている。今後、こうした取組みが進展していくに従って、社会福祉サービス事業者が非行・犯罪行為に至った人への支援に関わる機会は増えていくことが予想される。
しかし、これまで社会福祉の分野では非行や犯罪行為に至った人に対する支援は決して一般的なものとなってこなかった。ごく一部の社会福祉施設等では支援が行われてきた実績はあるが、それによって得られた経験や知見はこれまで十分に蓄積・発信されてはこなかった。そのため、近年の制度整備の進展によってサービス提供者の役割を期待されるようになった支援者のあいだでは、戸惑いが大きいと言われる。
このような状況にあるにもかかわらず、福祉専門職を主な読者層に想定した、非行・犯罪行為に至った人への具体的な支援の内容、支援にあたって重要かつ不可欠な項目についての情報を一元的に提供する資料は不足している。本書では、非行・犯罪行為に至った人への具体的な支援の内容、とくに支援者の自己覚知、対象者との関係の形成や維持といった支援にあたって重要・不可欠な項目についての情報を提供し、実際に支援にあたる者の理解の促進、支援技術の向上に資することを目指す。