- 〈幕府〉の発見
-
武家政権の常識を問う
講談社選書メチエ 831
- 価格
- 1,870円(本体1,700円+税)
- 発行年月
- 2025年10月
- 判型
- 四六判
- ISBN
- 9784065413692
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 謎の集団・秦氏 復讐の日本史
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2026年01月発売】
- プロの撮り方オリジナリティーを極める
-
価格:2,860円(本体2,600円+税)
【2023年10月発売】
- 英雄伝説の日本史
-
価格:1,012円(本体920円+税)
【2019年12月発売】













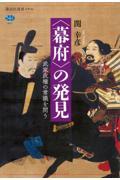











[BOOKデータベースより]
同じ武士でありながら、平氏や信長・秀吉の政権を「幕府」とは呼ばず、鎌倉・室町・江戸の政権のみを「幕府」というのはなぜだろうか。明治初期の歴史家・田口卯吉は「鎌倉政府」「徳川政府」と記し、江戸中期の新井白石は「王朝」に代わる「武朝」の優位を誇った。武士を否定した明治国家は、武家政権をどう理解したか。そして、脱亜入欧を目指す官学アカデミズムの新たな認識―「調教された武家政権」こそが〈幕府〉の本質だった。中世武士論と近代史学史の交差点から「日本」を問い直す。
序章 「幕府」の何が問題なのか?
[日販商品データベースより]第一章 幕府・政府・覇府『日本開化小史』の歴史観
第二章 「幕府」の発見『読史余論』から『日本外史』へ
第三章 近代は武家をどう見たか『国史眼』と南北朝問題
第四章 「鎌倉幕府」か、「東国政権」か 中世東国史の二つの見方
終章 「幕府」という常識を問う
「幕府」とはそもそも何か――。中国の文献に現れる「幕府」という語が、日本で「武家政権」を示す概念用語として使われるようになったのは、江戸時代後期のことという。ではなぜ、織田信長や豊臣秀吉の政権は「幕府」と呼ばず、鎌倉・室町・江戸の三つのみを幕府と呼ぶのだろうか。ここに、700年にわたって権力の座にあった「武士」の本質と、その歴史理解に苦慮してきた近代の歴史家たちの格闘の跡が見て取れる、と著者はいう。
たとえば、明治10年に刊行された『日本開化小史』には、「幕府」という用語は出てこない。著者の田口卯吉は、文明史的視点から「鎌倉政府」「徳川政府」あるいは「平安政府」と記しているのだ。では、江戸時代の代表的な史論『読史余論』や『日本外史』ではどうか? 明治期の帝国大学の教科書『国史眼』では「幕府」をどう位置づけているのか?
武家政権の否定から始まった明治国家が、日本中世を西洋中世に比肩する時代と位置づけ、自国史の脱亜入欧を果たすべく編み出したのが、「幕府」すなわち「調教された武家政権」という再定義だった。そして、この「幕府」の概念は明治維新(大政奉還と王政復古)の正当性を規定し、さらに南北朝正閏論争や、現在も続く日本中世史をめぐる議論にも大きな影を落としているのである。
著者の長年にわたる中世武士団研究と、史学史研究を交差させ、「日本史の常識」を問い直す野心作。
目次
はしがき
序章 「幕府」の何が問題なのか?
第一章 幕府・政府・覇府:『日本開化小史』の歴史観
第二章 「幕府」の発見:『読史余論』から『日本外史』へ
第三章 近代は武家をどう見たか:『国史眼』と南北朝問題
第四章 「鎌倉幕府」か、「東国政権」か:中世東国史の二つの見方
終章 「幕府」という常識を問う
あとがき
参考文献