この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- みたてのくみたて
-
価格:2,090円(本体1,900円+税)
【2024年07月発売】
- エンジニアリング組織開発
-
価格:3,080円(本体2,800円+税)
【2025年10月発売】
- 地球史マップ
-
価格:3,960円(本体3,600円+税)
【2024年01月発売】
- 「核抑止論」の虚構
-
価格:1,265円(本体1,150円+税)
【2025年07月発売】
- Androidアプリ開発のためのセキュリティ入門
-
価格:3,520円(本体3,200円+税)
【2025年11月発売】


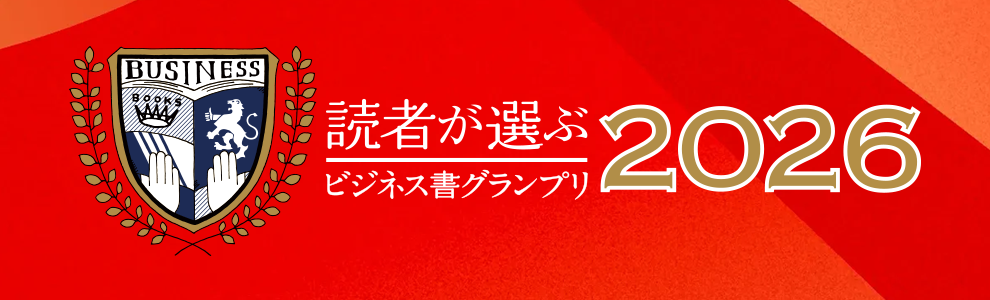

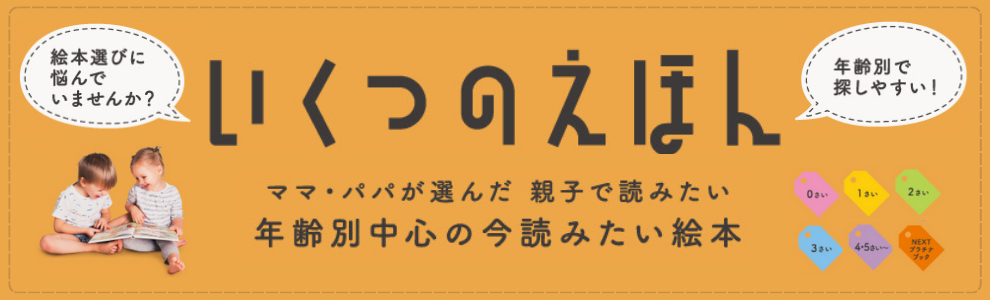









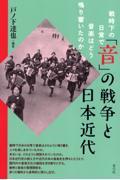



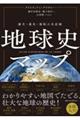








[BOOKデータベースより]
序章 日常に息づく戦時期の音楽文化(音楽文化の水脈;戦時期の音楽受容)
[日販商品データベースより]第1部 国内の音楽文化(日本の近代史をどう捉えるか―軍隊と社会の関係を中心に;戦前と敗戦後の音楽に関する連続性/非連続性―大阪朝日会館から考える;昭和初期・エロ・グロ・ナンセンスな世相と流行歌/唱歌―生きづらさに抗う大人/子どもの〈感情〉史 ほか)
第2部 海外と音楽文化の交差(近衛秀麿の過ごした戦時下のドイツ―音楽による日独外交という使命を帯びて 西洋音楽受容とともに歩んだ「国民音楽建設」とその戦後;植民地朝鮮における西洋音楽活動に関する試論―京城帝国大学教授夫人らと朝鮮人音楽家たちの相互関係を中心に)
終章 歌は美しかった―日本の「うた」への思い(「歌は美しかった」―その取り組み;演奏家の目からみた「うた」の諸相)
戦時下日本の日常で音楽はどのように鳴り響き、人々を楽しませていたのか。国内の音楽文化の諸相、海外事情と音楽の緊張関係などを事例に、戦前・戦後の連続性/非連続性という時間軸も織り込んで、敗戦後80年の2025年に「戦争と音楽」を鋭く問う貴重な成果。