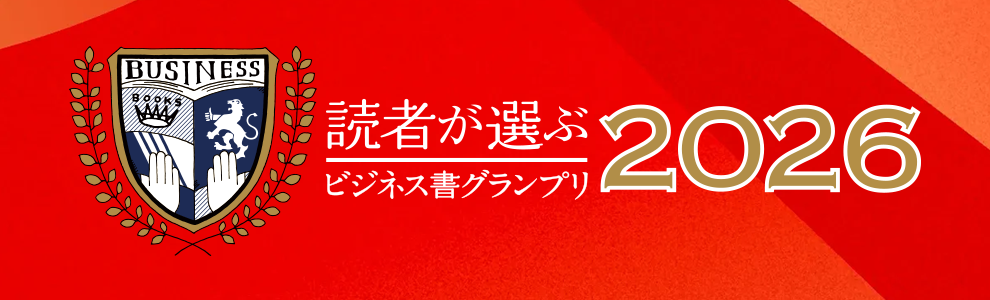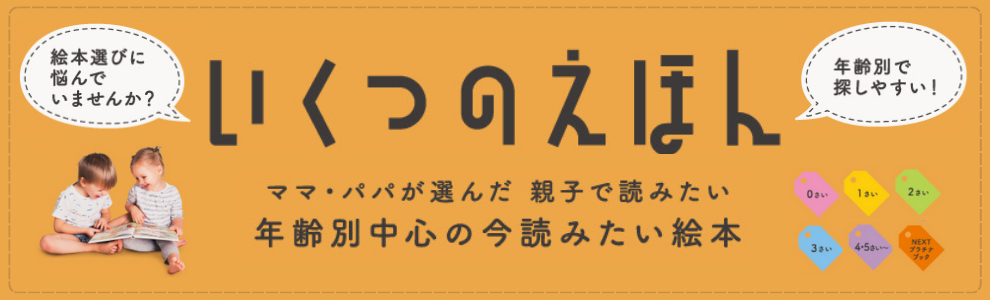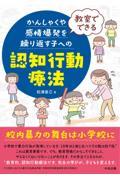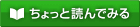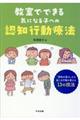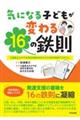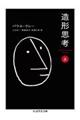[BOOKデータベースより]
小学校で暴力行為が急増しています。10年ほど前と比べてその数は約7倍。これは異常事態です。でも、教育現場だからこそできること、やらなくてはいけないことがあります。その手立てとなるのが、「教育的」認知行動療法です。先生の学びが、子どもを変えます。
序章 かんしゃくや感情爆発に振り回される教育現場
第1章 身につけよう!子どもと向き合う理論とスキル
第2章 認知の歪みと被害者意識
第3章 認知行動療法の進め方
第4章 認知行動療法の実践例
第5章 特別支援教育コーディネーターによる認知行動療法
★教師が本当に手を焼いている子どもは、「発達障害」でもなく「愛着障害」でもなく、かんしゃくや感情爆発を起こす子どもたち?★
近年、子どもの暴力行為が増加しているのは「小学校」です。文部科学省の調査結果では、1000人当たりの暴力行為発生件数は10年ほど前に比べて約7倍にものぼっています。これは、世界的にみても日本特有の事象です!そして、こうした子どもに対して「発達障害だから」「愛着障害だから」というレッテルを張って、専門家にまかせっきりにしてしまう教育現場を目の当たりにします。それらは大きな誤解です。かんしゃくや暴力行為を起こす子どもたちは、むしろ「反抗挑発症」や「間欠爆発症」の傾向があり、情緒や行動のセルフコントロールの脆弱性に起因すると考えられます。
◎大切なのは、障害や行動理由の特定ではなく、セルフコントロールの弱さに着目すること!◎
これらの子どもはDSM-5では「秩序破壊的・衝動制御・素行症群」の診断カテゴリーに入るであろうことが考えられます。しかし大切なのは、障害を特定することでも、なぜこんな行動をとるのかを特定することでもありません。彼らのセルフコントロールの弱さに着目して、教師として、教育的に指導することにあるのです。
◎「認知の歪み」も影響を及ぼしている!◎
こうした子どもは、「認知の歪み」が影響していることも見逃してはいけません。そこで教師が学ぶべきは、そして子どもたちに指導するべきことは、「教育的認知行動療法」なのです。行動が修正されれば認知も修正されて、適切な行動が定着すればセルフコントロール能力も高まります。教師は、学校という構造化を活用し、教育的認知行動療法のスキルを身に付けて子どもの自立を目指す、これこそが教育を施すということではないでしょうか。
本書では、いま手を焼いている子どもに対して教師が学ぶべきこと、やるべきことが実に具体的に解説されています。本当の教育とは何かを知りたい人に手にとってもらいた1冊です。
<こんな教員の方におすすめ>
・かんしゃくや感情爆発を起こす子どもに手を焼いている
・学校、教室でできる具体的な対応方法を知りたい
・教育現場における認知行動療法の活用を知りたい
【本書の特長】
・本当のクラス運営とは何かがわかる
・学校を、教育現場を活用することができる
・教師としてやるべきことが具体的にわかる
【主な目次】
はじめに
序章 かんしゃくや感情爆発に振り回される教育現場
第1章 身につけよう!子どもと向き合う理論とスキル
第2章 認知の歪みと被害者意識
第3章 認知行動療法の進め方
第4章 認知行動療法の実践例
第5章 特別支援教育コーディネーターによる認知行動療法
おわりに
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 教室でできる気になる子への認知行動療法
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2018年10月発売】
- 気になる子どもが変わる16の鉄則
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2022年07月発売】
- エピソードで学ぶ知的障害教育
-
価格:2,530円(本体2,300円+税)
【2014年10月発売】
- 障害のある子どもへのサポートナビ 改訂版
-
価格:2,310円(本体2,100円+税)
【2024年04月発売】
- クレヨンからはじめる幼児の絵画指導
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2008年02月発売】