この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 『ドラえもん』で哲学する
-
価格:968円(本体880円+税)
【2024年12月発売】
- 哲学者34人に、人生の悩みを相談してみた。
-
価格:869円(本体790円+税)
【2025年11月発売】
- 誰が「お寺」を殺すのか
-
価格:1,100円(本体1,000円+税)
【2025年10月発売】
- 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。
-
価格:924円(本体840円+税)
【2025年03月発売】
- 「当たり前」を疑う100の方法
-
価格:990円(本体900円+税)
【2024年03月発売】




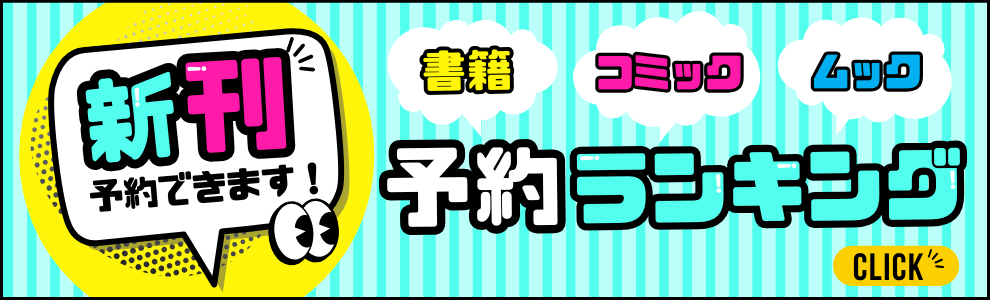








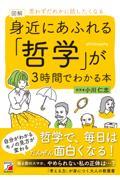

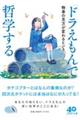


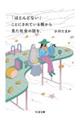






[BOOKデータベースより]
自分がわかるモノの見方が変わる。哲学で、毎日はだんぜん面白くなる!寝る前のスマホ、やめられない私の正体は…?「考える力」が身につく大人の教養。
第1章 いつもの景色を違う視点で―選択と発見にあふれる哲学(おにぎりはいつもツナマヨの私は、習慣の奴隷?コンビニの商品棚から考える「選択の自由と決断の不安」(ジャン=ポール・サルトル);「私、このままでいいのかな」と思ったらどうしたらいい?通勤電車の車窓から見る「存在と時間」の関係(マルティン・ハイデガー) ほか)
[日販商品データベースより]第2章 他者との境界線を引き直す―人間関係にあふれる哲学(他人と比べない自分になるにはどうすればいい?SNSの「いいね」から考える「承認欲求からの自由」(アルフレッド・アドラー);オンライン会議で心を通わせるコツとは?オンライン会議の沈黙から考える「共存在としての人間」(マルティン・ハイデガー) ほか)
第3章 環境に縛られない生き方―所有と消費にあふれる哲学(私が育てたこの野菜は、本当に私のもの?シェア畑から考える「所有権と自由権」(ジョン・ロック);なぜこんなにスマホに振り回されているの?故障したスマホから考える「物象化と阻害」(カール・マルクス) ほか)
第4章 自分のクセを客観視する―意志と習慣にあふれる哲学(二度寝の誘惑に負けない秘訣とは?朝のアラームを止める瞬間から考える「意志と表象」(アルトゥール・ショーペンハウアー);マニュアル通りに教えると新人は育たない?新人がなかなか育たない時に考える「経験主義と探究」(ジョン・デューイ) ほか)
第5章 人とうまく折り合うために―組織と社会にあふれる哲学(「みんな」に流されないために必要な心構えとは?みんなで渡る赤信号から考える「単独者と群衆」(セーレン・キルケゴール);民主主義の本質は、面倒くささの中にある?町内会の寄り合いから考える「一般意志と社会契約」(ジャン=ジャック・ルソー) ほか)
哲学って、実はこんなに身近だった!
日常のあらゆる瞬間が、哲学する時間に変わる
◎毎日のモヤモヤが、人生を変える「問い」になる
朝、アラームを止める手。なぜ勝手に動くの?
コンビニのおにぎり売り場で、なぜいつもツナマヨを選んでしまうの?
SNSの「いいね」。なぜこんなに気になるの?
実は、こうした何気ない日常の一コマに、2500年の哲学史が詰まっています。
本書は、誰もが経験する40の身近なシーンから、人生を豊かにする哲学的思考法を学べる大人の教養書です。
◎こんな「なぜ?」が解決します
? 寝る前のスマホがやめられない → デカルトが教える「私」の正体
? 既読スルーで心がざわつく → プラトンが説く恋愛の本質
? なぜかみんなで渡ると怖くない赤信号 → キルケゴールが警告する群衆心理
? 断捨離後の爽快感 → エピクロスが説く真の快楽
? 理不尽な要求への対処法 → アウレリウスが教える折れない心
本書を読むと、ふだん何気なく過ごしているだけの日常を俯瞰的に見る視点が得られ、自分のこと、周囲のことを一歩引いたところから考えられるようになります。
身近な事例から、自分軸を磨く「ことば」と「考え方」が身につく1冊です!
◎本書の3つの特徴
1. 専門用語ゼロでわかる
難解な哲学用語は一切使わず、誰でも理解できる言葉で解説。「イデア」も「弁証法」も、あなたの日常体験から自然に理解できます。
2. 今すぐ使える実践的な知恵
単なる知識の羅列ではなく、明日から使える具体的なヒントが満載。仕事の悩み、人間関係の葛藤、自分探しの迷い―――すべてに哲学的な解決法を提示します。
3. 東西の知恵を統合
ソクラテスからサルトル、孔子から西田幾多郎まで。西洋哲学と東洋思想のポイントを大つかみしながら、現代の日本人の感覚に合わせた事例で解説しました。
【目次】
第1章 いつもの景色を違う視点で−−−選択と発見にあふれる哲学
第2章 他者との境界線を引き直す−−−人間関係にあふれる哲学
第3章 環境に縛られない生き方−−−所有と消費にあふれる哲学
第4章 自分のクセを客観視する−−−意志と習慣にあふれる哲学
第5章 人とうまく折り合うために−−−組織と社会にあふれる哲学