この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- ケアする人の対話スキルABCD
-
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2015年03月発売】
- 持続可能な介護保険制度の考え方
-
価格:1,870円(本体1,700円+税)
【2022年09月発売】
- 地域に展く緩和ケア
-
価格:1,650円(本体1,500円+税)
【2020年11月発売】
- ケアシステム
-
価格:4,400円(本体4,000円+税)
【2023年03月発売】


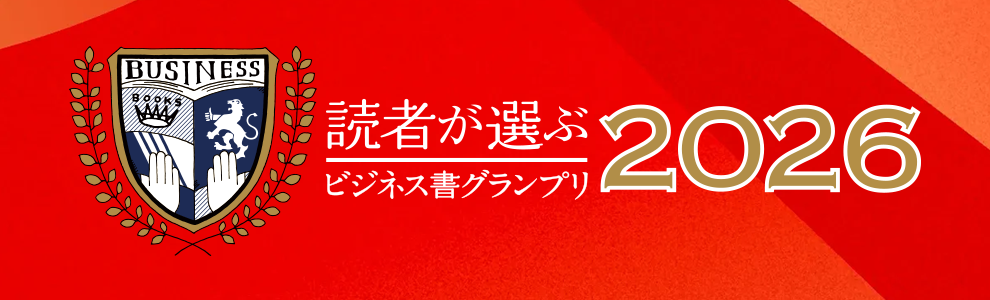

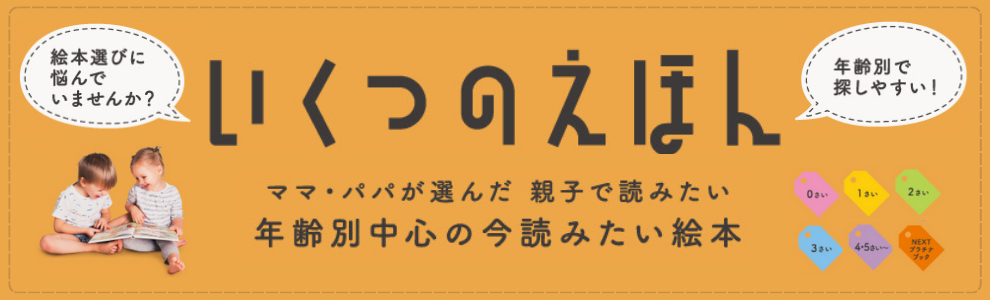












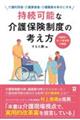




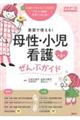
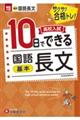
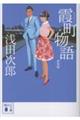



[BOOKデータベースより]
本人が決めるまで。判断に迷い、ときにいらだち、幸せをわかちあいながら。いっそう求められる障害のある人たちの「意思決定支援」。「待つ」ことを大切にした取り組みを咀嚼し、多機関・多職種による「連携」をカギに、今後の支援のあり方を考える。
第1章 障害のある青年の学び(KUPIでの学び 知はすべての人に開かれている;KUPIでの学びの魅力;エコールKOBEでの学び 障害のある青年も自分を変えることができる;そして生涯学習へとうねりは続く)
[日販商品データベースより]第2章 子ども、青年から学んだこと(二人の卒業生の生きてきた証;発達の視点で障害の重い子どもを理解する;青年の自立をサポートする)
第3章 意思決定支援とは?連携した取り組みと実践を通して考える(「意思決定支援」とは、どういうこと?;「私たちのことを私たち抜きに決めないで」 障害者権利条約と発達保障が背景に;問われてきた「本人主体」;連携(つながり)がキーワード)
2025年10月から始まる就労選択支援事業。障害者権利条約でも強調されている「本人主体」「意思決定支援」が具体的な施策の一つとして形になった側面がある。障害のある子ども・青年・成人たち「本人が決める」ことがいかに大切で、難しいものか。具体例からその内側にせまったとき、キーワードとして浮かび上がるのは「待つ」。多機関・多職種が連携しながら本人主体を支えるこれからをともに考えよう。