- アーリヤ人の誕生 新インド学入門
-
- 価格
- 1,210円(本体1,100円+税)
- 発行年月
- 2024年06月
- 判型
- 文庫
- ISBN
- 9784065359266
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- インダス
-
価格:6,050円(本体5,500円+税)
【2013年10月発売】
- セオドア・ルーズベルトと韓国
-
価格:2,750円(本体2,500円+税)
【1992年10月発売】
- 世界史の中の近代日韓関係
-
価格:2,640円(本体2,400円+税)
【2013年07月発売】
- 世界史のなかの東南アジア 上
-
価格:3,960円(本体3,600円+税)
【2021年12月発売】




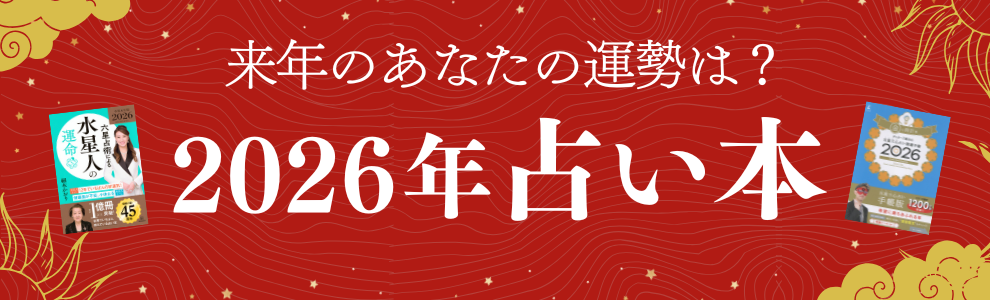






















[BOOKデータベースより]
インドとヨーロッパに広がる言語には共通の起源があるのではないか―。植民地インドでのサンスクリット語「発見」を端緒に、起源の言語の話し手として生み出された「アーリヤ人」は、瞬く間にナチス・ドイツの人種理論に繋がる強固な像を手に入れた。言語学誕生の歴史を追跡し、「すべての起源」インドに取り憑かれた近代西欧を克明に浮かび上がらせる!
第1章 インド学の誕生―十八世紀末から十九世紀初頭のインド・カルカッタ(ウィリアム・ジョーンズと言語学の誕生;ベンガル・アジア協会とウィリアム・ジョーンズに対する評価)
[日販商品データベースより]第2章 東洋への憧憬―十九世紀前半のヨーロッパ(オリエンタル・ルネッサンスをになった人々;印欧比較言語学の確立)
第3章 アーリヤ人侵入説の登場―十九世紀後半のヨーロッパ(系統樹説と印欧語族の故郷;マックス・ミュラーと「アーリヤ民族」)
第4章 反「アーリヤ人侵入説」の台頭―二十世紀のインド(インダス文明の発見と南アジア考古学の発達;一九九〇年代以降の反「アーリヤ人侵入説」とヒンドゥー・ナショナリズム)
第5章 私のインド体験―多様性との出会い(インド少数民族研究;私のムンダ語・ムンダ文化発見)
補章 出版二十年後に
ヨーロッパのラテン語・ギリシア語とインドのサンスクリット語に共通の祖となる、失われた起源の言語――。そんな仮想の言語の話し手として「アーリヤ人」は生み出された。そして、それは瞬く間にナチス・ドイツの人種論に繋がる強固な実体を手に入れる。近代言語学の双生児「アーリヤ人」は、なぜこれほどまでに人々の心を捉えて離さないのか。
言語学誕生の歴史から、「すべての起源」インドに取り憑かれた近代ヨーロッパの姿が克明に浮かび上がる!
「インド学」はインドで発達した学問ではない。18世紀末からサンスクリット語文献を集めてきたヨーロッパを中心に発達してきた。私たち日本人が抱く「インド」イメージもまた、近代ヨーロッパという容易には外しがたい眼鏡を通して形成されている。
植民地インドで「発見」された古典語サンスクリットの存在は、ラテン語やギリシア語との共通性から、ヨーロッパとインドに共通する起源の言語の存在を想像させた。類稀な語学の才に恵まれたイギリス人ウィリアム・ジョーンズ(1746-94年)によるこの「発見」によって、近代言語学は誕生する。同時にオリエンタリズムがヨーロッパを席巻し、『シャクンタラー姫』をはじめとするサンスクリット語文献が次々にヨーロッパで翻訳された。
その奔流のなかで『リグ・ヴェーダ』を英訳したのが、ドイツ出身で英国オックスフォード大学に職を得たフリードリヒ・マックス・ミュラー(1823-1900年)である。彼は比較言語学の成果から、『リグ・ヴェーダ』の成立年を紀元前1200年頃と推定し、「アーリヤ人の侵入」を紀元前1500年頃とした。日本の教科書でもよく知られる記述の源は、ここにある。
19世紀ヨーロッパで言語学とともに誕生した「アーリヤ人」は、20世紀にはナチス・ドイツによるユダヤ人迫害を生み、さらにはインダス文明が発見されたインドに逆流して、考古学的成果と対峙しながらさらなる波紋を生んでいく――。
近代言語学の双生児「アーリヤ人」は、なぜこれほどまでに人々の心を捉えて離さないのか。なぜ言語は常に民族という概念を呼び寄せずにいられないのか。言語学誕生の歴史をひもとくことで「起源」というロマンに取り憑かれ、東洋を夢見た西洋近代の姿を克明に描き出す。インドの実像に目を開く一冊。(原本:『新インド学』角川書店、2002年)
【本書の内容】
第1章 インド学の誕生ー―十八世紀末から十九世紀初頭のインド・カルカッタ
第2章 東洋への憧憬ー―十九世紀前半のヨーロッパ
第3章 アーリヤ人侵入説の登場ーー―十九世紀後半のヨーロッパ
第4章 反「アーリヤ人侵入説」の台頭――二十世紀のインド
第5章 私のインド体験ー――多様性との出会い
補 章 出版二十年後に