- 労働と身体の大衆文化
-
- 価格
- 6,050円(本体5,500円+税)
- 発行年月
- 2024年01月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784801007789
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 日中戦争下のモダンダンス
-
価格:6,600円(本体6,000円+税)
【2018年02月発売】
- 移動するメディアとプロパガンダ
-
価格:3,080円(本体2,800円+税)
【2020年03月発売】
- 激闘ニューギニア戦記
-
価格:785円(本体714円+税)
【2009年02月発売】
- もしも魔法が使えたら
-
価格:1,760円(本体1,600円+税)
【2017年07月発売】




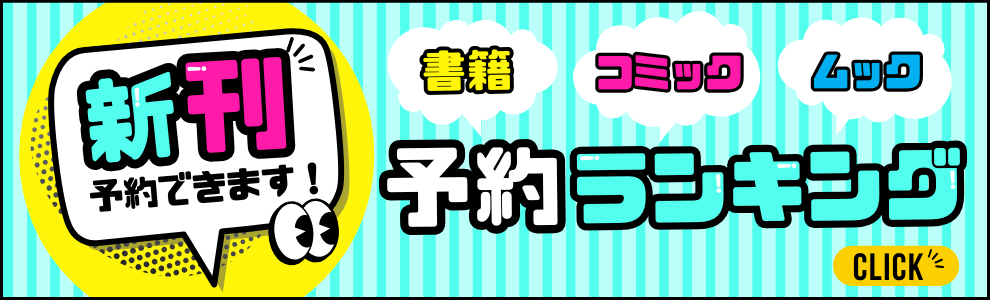













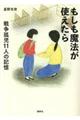





[BOOKデータベースより]
戦時下の舞台、芸術、合唱、ラジオ、映画を横断し、戦後の大衆文化へと至る伏流を探る。
第1部 侵犯される知覚、抵抗する身体(「ラジオ太郎」という「仮装」アナウンサーがいた;「木蘭従軍」の戦時期日本における“国民化”―東宝国民劇のアダプテーションに見る戦争とジェンダー;大衆文化としての体操と統制される身体;厚生運動とうたごえ運動―その連続性を見る;裁かれるエロス―戦後日本の揺らぐ文化イデオロギーと武智鉄二)
[日販商品データベースより]第2部 子どもの時間、少女の時(十五年戦争下の子供雑誌が描いた「科学日本」と「科学戦争」―『少年倶楽部』と『機械化』を中心に;戦時下・戦後の働く“少女”―雑誌『少女の友』を中心に;戦前戦後日本の少女文化におけるバレエ―『少女倶楽部』を中心に;“はれもの”にさわる子どもたち―児童文化における中国イメージの断絶と連続)
第3部 ポストコロニアル身体の展観(植民地近代、身体文化、ポップカルチャー―戦前戦後日本の舞踊芸術界の台湾に対する影響(一九二〇〜一九七九);日本軍政下インドネシアのPOW Camp謀略映画―映画の健全化の余剰としての「幻のフィルム」の語り;台湾映画「香蕉天堂(バナナ・パラダイス)」におけるバナナ表象―バナナを巡る記憶の構築がもたらす現代台湾史の視角)
プロパガンダ大衆文化の行方
翼賛体制下、国民の身体は総力戦に向け保全されるべきものとなり、国威発揚と労働・生産を下支えする大衆文化が次々と生まれた。では動員解除後、娯楽を享受する身体は何を求め、大量に生産された娯楽はどこへいったのか。戦時下の舞台・芸能・合唱・ラジオ・映画を横断し、戦後の大衆文化へと至る伏流を探る。