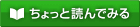[BOOKデータベースより]
「公家衆法度」を定めた江戸幕府による統制の下、先例や伝統などを重視する因習的な世界に沈滞していた公家は、幕末になぜ浮上しえたのか。近世の公家日記を読み解き、現状を変革していこうとする政治意識の芽生えを追究。儒学や有職研究などの学問を通じて公家が自己形成を実現させ、新しい政治主体を形成させていく過程を実証的に明らかにする。
序章 研究史整理と本書の課題
第1章 近世公家社会における葬送儀礼
第2章 野宮家における家業の継承―野宮定之を事例として
第3章 一八世紀公家社会における学問と家業―滋野井家を事例として
第4章 近世公家社会における一門―勧修寺一門を事例として
第5章 家礼関係に見る家礼の役割
第6章 三条実万の学問履歴
第7章 幕末公家社会における三条実万の役割
第8章 学習院学問所設立の歴史的意義
第9章 幕末の修陵事業―朝廷側の視点から
終章 近世公家社会と有職故実
「公家衆法度」を定めた江戸幕府による統制の下、先例や伝統などを重視する因習的な世界に沈滞していた公家は、幕末になぜ浮上しえたのか。近世の公家日記を読み解き、現状を変革していこうとする政治意識の芽生えを追究。儒学や有職研究などの学問を通じて公家が自己形成を実現させ、新しい政治主体を形成させていく過程を実証的に明らかにする。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。