この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 児童養護施設のエスノグラフィー
-
価格:4,950円(本体4,500円+税)
【2023年12月発売】
- マンガでわかる社会学
-
価格:2,090円(本体1,900円+税)
【2012年11月発売】
- ベーシック・インカムの哲学 新装版
-
価格:6,600円(本体6,000円+税)
【2009年12月発売】
- 安全学入門 第2版
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2023年03月発売】




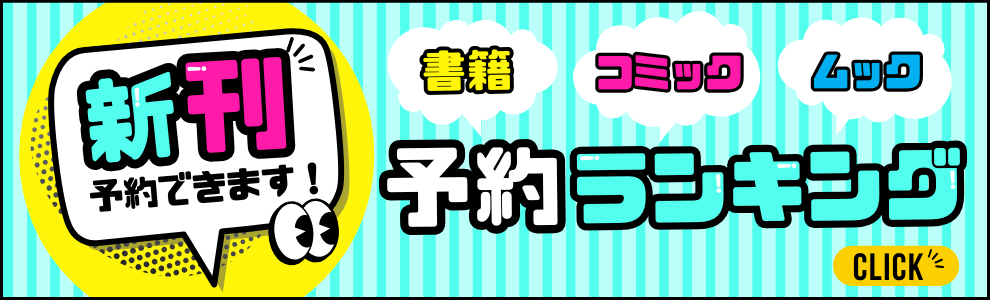



















[BOOKデータベースより]
今日、疫病と戦争によって国家間の分断が深刻化する中、多くの国が文化外交に力を入れている。この文化外交は、日本の場合、1930年代に「国際文化事業」として誕生した。本書では、この戦前戦中期の「国際文化事業」が戦後日本の外交・政治・文化・教育の各方面に与えた影響について考察する。
第1章 堀田善衛と戦時下の国際文化振興会―国際文化交流史研究の観点から『若き日の詩人たちの肖像』を読む
第2章 日本のオランダ語教育とオランダの日本語教育の変遷―長崎とライデンを中心に
第3章 オーストラリアの日本語教育を日本の新聞はどのように報道してきたか―その一〇〇年の変遷
第4章 戦前戦中期にオーストラリアで制作された日本語教科書―とくに、その意図せざる「結果」について
第5章 鶴見祐輔と一九三〇年代のオーストラリアにおける日本語教育―「日本語熱」の発見とその戦中戦後への影響
第6章 中島敦の『山月記』と釘本久春―はたして釘本は「袁〓」だったのか
第7章 敗者たちの海外言語普及―敗戦後における日本とドイツの海外言語普及事業
第8章 戦前戦中期における文部省直轄学校の「特設予科」制度―長崎高等商業学校を事例として
第9章 戦前戦中期における文部省直轄学校「特設予科」の留学生教育―長崎高等商業学校の場合
第10章 旧制浦和高等学校のアフガニスタン人留学生―どうして彼は浦和で学ぶことになったのか
第11章 三島由紀夫著『豊饒の海』とタイの留学生―「シャムの王子」たちのモデルは誰か