この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- グローカルな視点から考える欧米の世界と文化 演劇・音楽・経営編
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2024年09月発売】
- 安川沿い
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2021年01月発売】
- ピアノを弾くからだ 指のトレーニング編
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2023年05月発売】
- さぷりキッズ 1
-
価格:1,100円(本体1,000円+税)
【2023年06月発売】
- 徹底攻略 全調スケール集
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2022年11月発売】













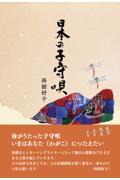




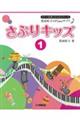






[日販商品データベースより]
全国に何万とある子守唄。母親の数だけあるとすれば膨大な数にならざるをえません。赤ん坊を寝かしつける目的で歌われる唄ですから複雑で難解というものはありません。しかし、歌う人は百人百様、歌詞は無限にあり、意味不明のものも散見しています。
西舘好子さんは二十数年にわたって日本中の子守唄を探し歩きました。そして子守唄が果たしてきた役割を考え続けてきました。やがてひとつの答えにいきつきます。
――母親はシンガーソングライターとなって独自の想像力でさまざまな言葉を編んでいきます。子守唄の歌詞には母親の愚痴や不平不満も盛り込まれるものです。おそらくその正直な本音こそが、人が信頼関係を築く基本の一歩なのだと私は思います。
大家族の時代はすでに遠く、核家族が当たり前になっていた中で行き詰まりを見せる親子関係。それは子ども受難の時代の始まりでした。西舘さんは世代をつないで編まれてきた「子守唄」こそ、病める現代社会の処方箋になると信じています。
西舘さんは本書で訴えます。「子守唄はなくしていけない歌なのです。人間がいる限り」