この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 高風味・無病のトマトつくり
-
価格:1,603円(本体1,457円+税)
【1995年02月発売】
- 畜産学
-
価格:7,150円(本体6,500円+税)
【2023年11月発売】
- 種を育てて種を育む 改訂版
-
価格:1,650円(本体1,500円+税)
【2023年07月発売】
- いちばんよくわかる超図解土と肥料入門
-
価格:1,650円(本体1,500円+税)
【2016年08月発売】


















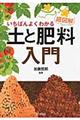





[BOOKデータベースより]
1 大豆の誕生
[日販商品データベースより]2 大豆食品について
3 大豆の近代史
4 国内で持ち上がった大豆粕の需要
5 満州における大豆の歴史
6 満鉄の大豆ビジネス
7 満州国と日本の大豆産業
8 日本企業が満州の大豆事業に
9 日中戦争と満州大豆
10 欧州における大豆の発展
11 アメリカ大豆について
12 戦争で飛躍するアメリカ大豆
13 アメリカで発展した大豆産業
14 フォード自動車と大豆
15 第二次世界大戦でアメリカ大豆が飛躍
16 日本の戦後の食糧難
17 アメリカ大豆のつまずきと南米の抬頭
18 世界の大豆栽培
19 戦争と大豆の裏面史
20 満鉄が開発したもうひとつの抽出技術―満鉄が研究したアルコール抽出技術
大豆は不思議な生命力をもった植物だと思わずにはいられません。大豆がこの世に生まれてきたのは今から5千年ほど前、中国、韓国とほぼ同じ時期に、我が国にも野生のツルマメから変身して大豆が生まれたのです。古代の縄文人たちがいかに長い時間をかけてツルマメの栽培を繰り返していたことか、そして繰り返し種を蒔いている時に、より大きな種子を選んで種まきをするという努力を繰り返したことによって、現在のような大粒の大豆に変身したと考えられます。
私たちが最もイメージしやすい大豆の利用は、日常の食卓に現れる食品への用途ではないでしょうか。今日一日に自分が食べた食事を振り返ってみると、いかに私たち日本人の食生活が大豆食品を利用しているか、改めて驚かされることでしょう。
しかし、それらには奈良時代や平安時代に、中国や朝鮮半島から持ち込まれた東アジアの食文化の影響や、寺院や民衆の中で作り上げられてきた食の歴史が何層にも積み重ねられていることにも思いめぐらしておきたいものです。
そして大豆はここ百余年の間にアジアの一隅から世界に飛び出していった、激動の歴史を持っているのです。そこには満州という、今では存在していない中国東北部を出発点として、世界戦争にも遭遇しながら大豆の活躍の舞台が世界へと広がっていきました。