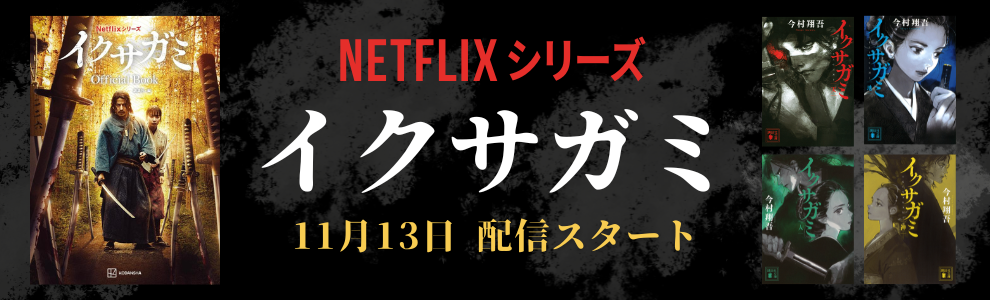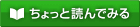[BOOKデータベースより]
一九六八〜七九年(一九六八年四月、「教研集会にみる教育行財政問題」『住民と自治』59号(土屋基規と共同執筆)(六八〜七六頁)(一〇);一九七二年八月五日、「学校統廃合について」『教育通信』673号(高知県教組)(三頁)(八二) ほか)
一九八〇〜八九年(一九八〇年三月、「過密・過疎、へき地の教育」『教育評論』八〇年臨時増刊号(一六六〜一六九頁)(一九一‐二);一九八〇年三月二〇日、「教育財政と教育条件整備」『子どもの権利と教育法』(日本教育法学会年報9号、有斐閣)(一五六〜一六六頁)(一九二) ほか)
一九九〇〜九九年(一九九〇年一月一五日、「教育条件整備の運動」『日本の教育 第三八集』(四〇九〜四〇九、四一二〜四一三、四一五〜四一七頁)(四七三);一九九〇年一月一五日、「教育条件整備の運動」『日本の教育 第38集』(日本教職員組合) ほか)
二〇〇〇〜二〇〇九年(二〇〇〇年一月、「学級規模と学校規模をどう考えるか」『母と子』(四〜一三頁)(七七六);二〇〇〇年二月二九日、「学校改革と教職員定数配置の行方―12・4シンポジウムの報告」『子どものための学校事務』68号(二〜七頁)(七七九) ほか)
二〇一〇〜二〇一八年(二〇一〇年一一月、「教育の無償化・少人数学級の意義と教育条件」『議会と自治体』151号(八九〜九六頁)(一〇三一);二〇一三年年九月一六日、「危機の時代と教育条件確立の展望」『と〜く』号(二〜八頁)(一〇七六) ほか)
教育財政学の第一人者として知られる著者が教育現場のありようを鋭く問う。深い学識・見識に支えられた論文の数々を集成。教育学を学ぶための必備の図書。
A5判上製(ケース付き)
第3巻「学級規模、学校規模・統廃合・施設など)」の分野は一般に「教育条件」と称され、教育行政学、教育財政学の主要な研究分野である。「教育条件」は戦前の「七〇人学級」に代表されるように国の教育行政に軽視された。その反省から戦後教育改革で「教育条件」は重要な教育的価値として認識され、教育基本法一〇条(一九四七年三月)にその整備が教育行政の任務と規定され、教育行政学、教育法学の主要なテーマとなった。(「第3巻「学級規模、学校規模・統廃合など」の解説」より)
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- ベイシス数学2B+ベクトル 改訂版
-
価格:1,100円(本体1,000円+税)
【2024年10月発売】
- ランダム総点検英文法・語法最終チェック問題集 基礎レベル編
-
価格:1,210円(本体1,100円+税)
【2022年09月発売】