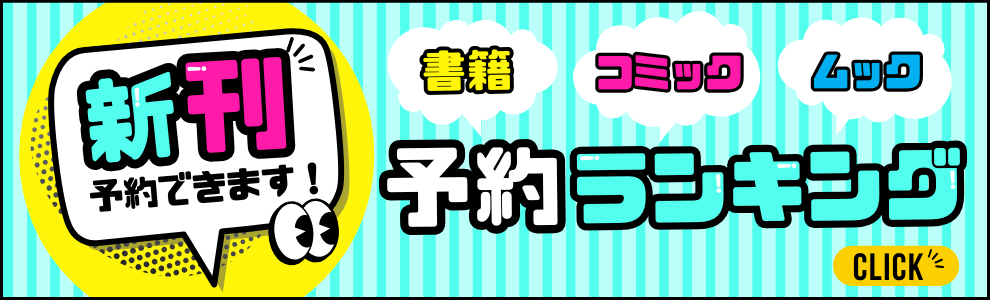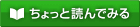[BOOKデータベースより]
中世後期から近世にかけて、どのように村落の「自治」が形成され、幕藩体制下における社会の基礎単位としての村が登場するのか。その経緯と背景を、和泉・紀伊・丹波の村落を事例に、惣有地、「自治」、近世村落との関連、「日常」の四つの視角から再検討。領主層をはじめとする上位権力と村落・地域との「日常」面での結び付きに焦点を当て実態に迫る。
課題と方法
第1部 戦国期初頭における荘園領主の機能(戦国期和泉国日根荘における根来寺僧の動向と荘園領主;戦国期和泉国日根荘にみる代官請負の意義;中世後期の上位権力と地域社会―和泉国日根荘を中心に)
第2部 村落の変容と「自治」の形成(惣有地の形成・経営と上位権力―紀伊国相賀荘柏原村を中心に;在村寺社の経営と「村落「自治」」―紀伊国柏原村の証誠権現社を題材に;柏原村の証誠権現社について―古文書原本調査から分かったこと;「村中」形成の背景と歴史的意義―紀伊国相賀荘柏原村を題材に)
第3部 中間層と「村落「自治」」(中世後期における中間層の動向と「村落「自治」」―紀伊国柏原村の神主を題材に;中近世移行期における村落と領主の関係―丹波国山国荘を中心に)
まとめと展望
中世後期から近世にかけて、どのように村落の「自治」が形成され、幕藩体制下における社会の基礎単位としての村が登場するのか。その経緯と背景を、和泉・紀伊・丹波の村落を事例に、惣有地、「自治」、近世村落との関連、「日常」の4つの視角から再検討。領主層をはじめとする上位権力と村落・地域との「日常」面での結び付きに焦点を当て実態に迫る。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 僧兵盛衰記
-
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2017年01月発売】