この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- カラー版 名画でわかるヨーロッパの24時間
-
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2026年01月発売】
- ドラえもんと学ぶ日本美術超入門
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2025年07月発売】
- 若冲になったアメリカ人 ジョー・D・プライス物語
-
価格:759円(本体690円+税)
【2024年09月発売】


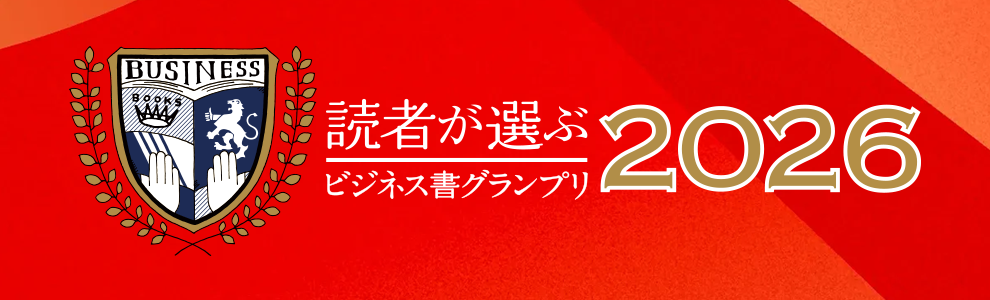

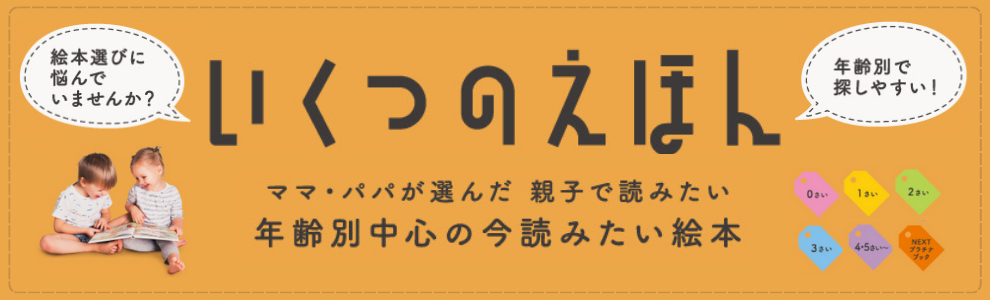
























[BOOKデータベースより]
近代日本において、整備が遅れた公立美術館の代替機能を果たしてきたのは民間企業であった。三井・三越の高橋義雄・日比翁助を軸に経営者の系譜をたどり、その経歴や美術観を通して、企業経営に美術が導入されてゆく背景を論じる。
序章 百貨店と美術
[日販商品データベースより]第1章 近世の見世物から近代の展示へ
第2章 米国百貨店のアート・ギャラリー
第3章 日本美術の発見と美術振興
第4章 三越呉服店の経営と美術
第5章 財閥当主のパトロネージ
第6章 江戸の名所から東京の新名所へ
終章 実業家の美術蒐集と公開
日本近代の発展過程で、整備が遅れた公立美術館の代替機能を果たしてきたのは民間企業であった。本書は企業と美術の関係性を、とりわけ先駆的であった三越を中心に明らかにする。三井・三越の高橋義雄・日比翁助・三井高棟、三菱岩崎家の人々、大倉喜八郎、根津嘉一郎、石橋正二郎、さらには西武の辻井喬(堤清二)に至る経営者の系譜を辿り、彼らの経歴や美術観を通して、企業経営に美術が導入されてゆく背景を論じる。