この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- リスク大国日本
-
価格:1,650円(本体1,500円+税)
【2022年04月発売】
- 現代日本図書館年表1945ー2020
-
価格:1,100円(本体1,000円+税)
【2022年01月発売】
- これからはじめる周術期等口腔機能管理マニュアル 第2版
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2020年02月発売】













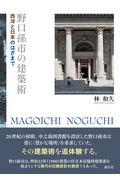



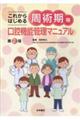
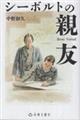









[日販商品データベースより]
20世紀初頭、
中之島図書館を設計した野口孫市は
常に〈豊かな場所〉を希求していた。
その建築術を追体験する。
*
野口孫市は1891年(明治24)に東京帝国大学工科大学造家学科に入学、明治建築界の重鎮・辰野金吾の薫陶を受けた。大学院を卒業し逓信省に3年勤めた後、1899年(明治32)、住友に招かれた。1年余りの欧米建築事情調査に派遣され、1900年、住友本店臨時建築部が発足すると初代技師長に就いた。住友本店臨時建築部は後に世界有数の設計会社となる日建設計の原点である。
野口は47歳で亡くなるまで、建築家人生は19年と短いながら、大阪図書館(後の大阪府立中之島図書館)、住友家須磨別邸、日暮別邸、住友活機園(旧伊庭貞剛邸)など数々の名作を残した。
辰野ら明治の建築家第1世代が西洋から「ものとしての建築」を直接的に移入していたのに対し、第2世代に当たる野口は様式的な規範にとらわれず、その建築がどうあるべきかを多角的に考え、建築の本流と言える手法でもって本質的な型から組み立てていった。
たとえば、中之島図書館は西洋古典主義建築様式の習熟を示す顕著な例であるが、野口は大阪という都市の中之島という場にこの図書館が存在することの意味を考え、建築的思考としての「場所と幾何学」を実現させた。中之島図書館は1974年(昭和49)、国指定の重要文化財となったが、今日でも現役の図書館として多くの府民に利用されている。
中之島図書館とほぼ同時期に着手した須磨別邸は、中之島図書館とはまったく異なり、当時の英国や米国東海岸における建築の新潮流によるものだった。西洋古典様式の左右対称の形式的な規範から脱し、日本で初めて自由な構成による建築を実現した。住友家の迎賓館として設計された日暮別邸では、様式主義的な装飾を削り落とし、空間の構成だけで豊かな場所を作り出した。これは後のモダニズム建築への胎動と捉えられる。
西洋建築のあらゆる手法を自家薬籠中のものとしていた野口だが、自邸を含めて和風住宅建築も手がけている。大工棟梁・二代目八木甚兵衛や「植治」として知られる庭師・七代目小川治兵衛らとのコラボレーションも着目される。
このように、西洋と日本のはざまで、人々が場所のもつ意味の豊かさを体感できる器としての建築をつくることが野口の目的だった。
*
本書は、日本近代建築史において重要な位置にありながらこれまであまり光を当てられなかった野口の建築術の核心に迫り、その特徴を明らかする。また、野口が生きた時代や、生い立ちから住友に籍を置くまでの過程も丹念にたどり、建築思考と建築技術を結びつける野口の建築術誕生の背景にも言及している。建築写真や図面、学生の頃からのスケッチなどカラーを中心に約400点の図版を収載。