[BOOKデータベースより]
地震がおきたら、どうしよう。もし、ひとりでいるときだったら?消防士さんは助けてくれる?どんな時でも、どんな場所でも、子どもたちが、自分で自分のからだを守り、また、協力して助けあうことが大切です。学校で家庭で必読の一冊。緊急連絡先を書こめるかぞくのやくそくカードつき。
[日販商品データベースより]地震がおきたらどうするの? さいしょになにをしたらいいんだろう?
子どもたちにわかりやすく、自分の身を守ることを伝える防災絵本。
もし閉じこめられた時にはどうしたらいい?
家にいるときは? 外で地震にあったら? 海の近くでは?
やさしい絵でわかりやすく小さい子にも伝えます。
1995年阪神・淡路大震災を経験した神戸の現役消防士が考えた、こどもたちに伝える地震の絵本。
自らの経験をもとに、地震がおきたときの心構えをやさしく、わかりやすく伝えます。
何度もくりかえし読んで、地震や津波に備えたい、学校や家庭に必携の絵本。
原案:谷敏行(神戸市消防局) 企画・協力:神戸市消防局
巻末には地震にそなえる防災情報ページを掲載
緊急連絡先を書きこめる「かぞくのやくそくカード」つき
読み聞かせに最適な大型ボードブック絵本 ?(978-4-7764-0958-8) もあります。

















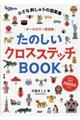




けんちゃんは小学3年生。ゆうちゃんは小学1年生。2人は学校から帰ってきて、避難訓練をしたことをお母さんに話します。地震が起きたときは「しせいを低く」「頭を守って」「動かない」こと。避難するときは「おさない」「はしらない」「しゃべらない」「もどらない」こと(「お・は・し・も」の約束)。消防士さんから学んだことを口々に報告する2人に、お母さんはびっくりするようなことを話してくれます。それは、昔この街が地震で、建物がたくさんこわれて中がぐしゃぐしゃになったとき、お母さんは小学3年生だったこと。こわれた建物のなかにとりのこされて「助けてー」と叫んだこと。でも消防士さんは、まずは火を消さなければならなかったこと……。初めて聞くお母さんの話に、けんちゃんもゆうちゃんもびっくりしながら耳を傾けます。地震を経験したお母さんとの会話のなかで、けんちゃんとゆうちゃんは、もし地震が起きたら、自分たちはどんなふうに動かなくてはいけないのかをだんだん学んでいきます。地震がおきて閉じ込められたら、「助けて!」と声を出すこと。声を出せなかったら、何かをたたいたり笛をふいたりして音を出すこと。また、閉じ込められている人を見つけたら、大人やまわりの人に知らせること。揺れている間は身を守り、揺れがおさまったら家の中でつかっている火を消すこと。火事が起きたら、小さい火のうちにみんなで力をあわせて火を消すこと。津波が起こるかもしれないから、高いところに逃げること……。本書は神戸市消防局の企画・協力で作られた本。1995年に起きた阪神・淡路大震災の教訓が具体的に盛り込まれ、とても実用的な内容になっています。地震が起きたとき、何がいちばん大事なのかを、絵本の形式で教えてくれます。親子の会話でお話がすすみ、最後には家族で地図を広げて、危ないところがないかを確認したり、連絡方法・防災グッズを確認したりという場面まで描かれます。巻末には「家族を守る防災知識」と題して、神戸市消防局から伝えたいことが、具体的な資料などとともに6ページに渡ってまとめられています。家の中を子どもの目線でチェックすること、断水・火災にそなえてお風呂に水をためることなど、親子の “心の備え”となること間違いなし。地震の多い国に住むわたしたち。この一冊が、子どもの一生を守るかもしれません。ぜひ家族で読んでみてください。
(絵本ナビライター 大和田佳世)
私も小学生の時に阪神大震災を経験しました。
最近では大阪北部地震も。
ですので、他人事とは思えないお話でした。
震災が起こると、誰か助けが来てくれる。
そう思っている人は多いと思います。
しかし、実際は、消防士さんたちは火消しが優先。
絵本のお母さんのように壊れたお家の中に取り残されても誰も気づいてくれないかもしれません。
自分の身は自分でまもる。限界はありますが、改めてそう気づかされました。
学校の避難訓練等では、なかなかこのようなことは教えてくれませんよね。是非、学校などでも読んで頂きたいです。(tori.madamさん 30代・大阪府 女の子6歳、女の子3歳)
【情報提供・絵本ナビ】