この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 破産者たちの中世
-
価格:880円(本体800円+税)
【2005年07月発売】
- 岩波講座日本歴史 第8巻(中世 3)
-
価格:3,520円(本体3,200円+税)
【2014年08月発売】
- 岩波講座日本歴史 第9巻(中世 4)
-
価格:3,520円(本体3,200円+税)
【2015年02月発売】
- 岩波講座日本歴史 第6巻(中世 1)
-
価格:3,520円(本体3,200円+税)
【2013年12月発売】
- 岩波講座日本歴史 第7巻(中世 2)
-
価格:3,520円(本体3,200円+税)
【2014年04月発売】


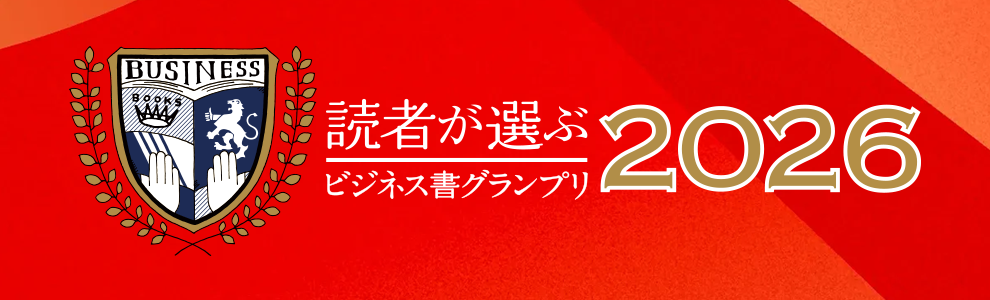

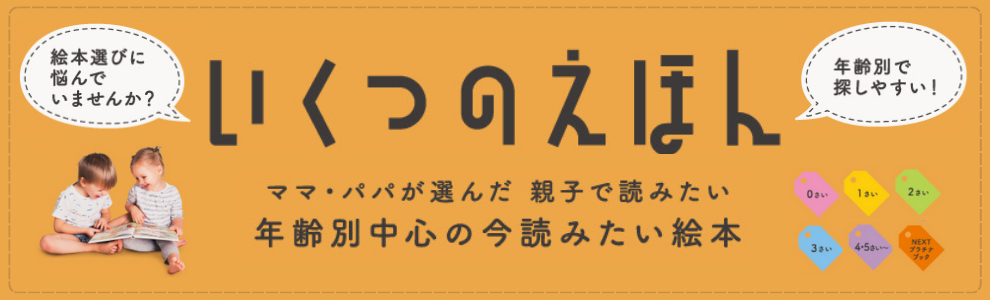





















[BOOKデータベースより]
「贈与経済は極限まで進むと市場経済ときわめて近いものになる。」『贈与の歴史学』(角川財団学芸賞)の俊英による、鮮やかな中世社会論。「成熟した儀礼社会」とは、非ポトラッチ社会の互酬とは。
序論
[日販商品データベースより]第1章 中世の贈与について
第2章 折紙銭と一五世紀の贈与経済
第3章 「御物」の経済―室町幕府財政における贈与と商業
第4章 宴会と権力
第5章 銭貨のダイナミズム―中世から近世へ
第6章 中世における物価の特性と消費者行動
第7章 精銭終末期の経済生活
第8章 借書の流通
終章 中世における債権の性質をめぐって
中世日本は贈与社会が行き着くべきひとつの極限段階を示していた。日本史上最も贈答儀礼が肥大化したこの時代、贈与経済と市場経済は対立的でなくきわめて親和的な関係を築いていた。『贈与の歴史学』(中公新書)で角川財団学芸賞を受けた俊英による鮮やかな日本中世社会論である。
貨幣そのものを人に贈るという習慣も室町時代にはじまるが、贈答額を記した目録が事実上の約束手形に転化し、後日決済や相殺、流用、催促や取引もおこなわれる特異な「折紙銭」が、著者の贈与研究のきっかけであった。計算・打算・信用といった市場経済的な観念がその対極にあるとみられがちな贈与の世界にも浸透した、まさに「成熟した儀礼社会」の様相である。
「与える権力」から「受け取る権力」へ変質した室町幕府の贈与依存型財政。東山御物の形成や日明貿易にもかかわる贈答品市場。身分制社会すなわち非ポトラッチ社会の宴会と権力。自国通貨を鋳造しなかった中世から近世への移行期にかけて価値の生滅をくりかえした銭貨のダイナミズム。季節・地域間の物価変動のメカニズムを知悉していた消費者行動、その一方で贈与名目で支払われる硬直的な賃金と労働観の問題。借書の流通や折紙の譲渡を可能にした根本原理としての債権の譲渡性は、極端に高まって贈与すら非人格化したが、16世紀に一転して鈍るのはなぜか。モース、ブローデル、ポランニーをも視野に収め、日本中世社会の特質と変容を論じ、じつにドライで合理的な中世人の精神にまで迫る。