[BOOKデータベースより]
第1章 非侵襲脳機能計測とは
第2章 脳の構造と機能局在
第3章 神経活動と脳血流反応
第4章 脳波(Electroencephalography)
第5章 脳磁図(Magnetoencephalography)
第6章 磁気共鳴画像(Magnetic Resonance Imaging:MRI)
第7章 近赤外線スペクトロスコピー(Near‐Infrared Spectroscopy:NIRS)
第8章 PET/SPECT(Positron Emission Tomography/Single Photon Emission Computed Tomography)
第9章 経頭蓋磁気刺激(Transcranial Magnetic Stimulation:TMS)
第10章 脳機能イメージングの今後の展望
第11章 おわりに
医学、工学、心理学で脳科学に携わる4人の著者が、様々な非侵襲脳機能計測法の計測原理と、それらがどのように脳研究に使われているのかを、カラーの図を用いながらわかりやすく説明する。


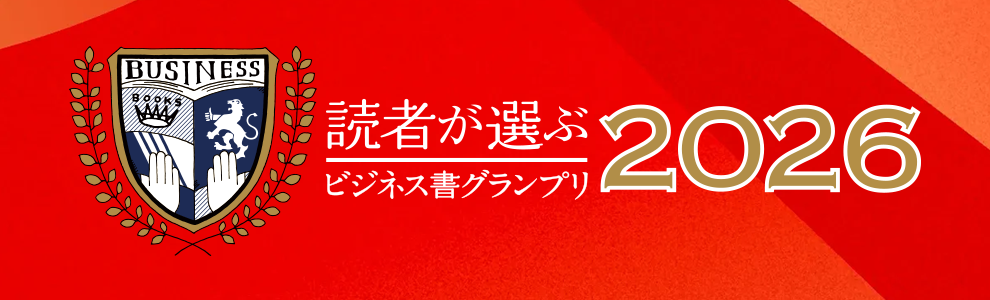

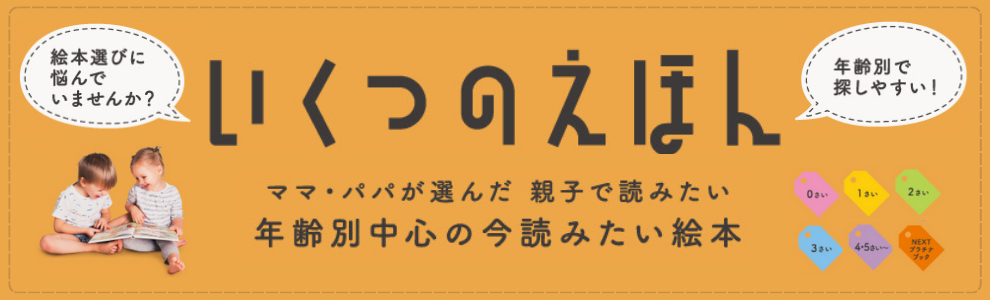
















近年脳機能計測法が多様化・複雑化したことに伴って医学実験心理学情報工学から物理学数学まであらゆる自然科学分野の研究者によって脳科学の研究が進められている。脳科学の本質とは私たちの行動と脳活動との多様な相関関係を生み出している脳のメカニズム法則を洞察し仮説を立て検証していくことであり脳機能計測がその手段となる。行動と脳活動との表面的な相関関係をみるのではなく本質に迫ろうとするには各計測法の計測原理や計測中のノイズの特性を理解した上で脳活動を計測・解析しなければならない。
そこで本書では医学工学心理学で脳科学に携わる4人の著者が多くの分野で脳研究を志す人たちへ向けさまざまな非侵襲脳機能計測法の計測原理とそれらがどのように脳研究に使われているのかをカラーの図を用いながらわかりやすく説明する。