この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 子どものウェルビーイングとムーブメント教育
-
価格:2,530円(本体2,300円+税)
【2024年06月発売】
- 0歳児から主体性を育む保育のQ&A
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2019年04月発売】
- 保育内容指導法「言葉」
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2019年12月発売】
- 乳児保育 第4版
-
価格:2,310円(本体2,100円+税)
【2022年03月発売】
- 発達障がい児の育成・支援とムーブメント教育
-
価格:2,530円(本体2,300円+税)
【2014年07月発売】


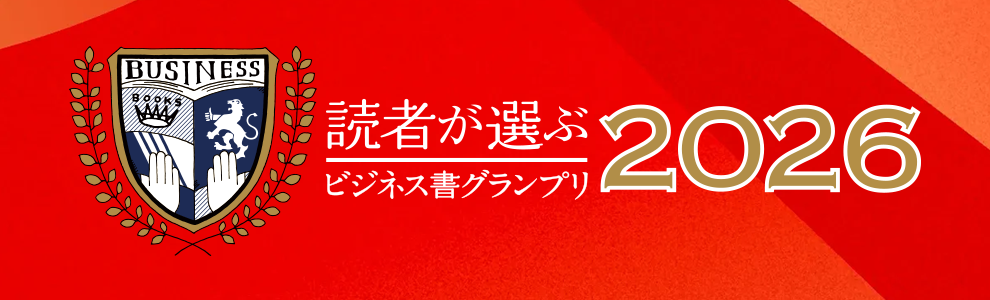

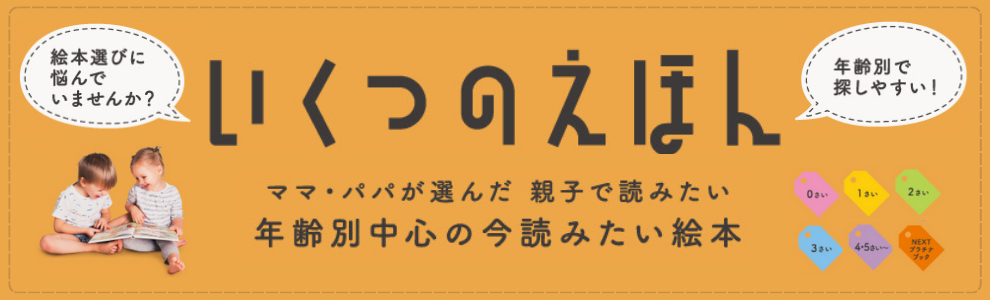









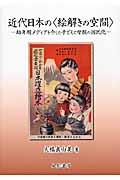














[BOOKデータベースより]
序章 幼年用メディアを介した子どもと母親の国民化を研究することの意義
[日販商品データベースより]1章 “赤本”と呼ばれた絵本の成立、そして排除から包摂へ―絵本の生産・流通・受容を巡る諸問題
2章 絵雑誌の出現と子どもの国民化―『お伽絵解こども』(1904‐11)に見るジェンダー
3章 家庭教育メディアとしての絵本―金井信生堂の創業期絵本(1908‐23)に見る“暮らしのイメージ”
4章 エージェントとしての“お母様方”の成立―倉橋惣三と『日本幼年』(1915‐23)の広告
5章 『子供之友』17〜25巻(1930‐38)のメディア・イベント―「甲子上太郎会」と「甲子さん上太郎さんたち」
6章 “講談社の絵本”(1936‐44)に見る総力戦の道筋―『講談社の絵本』(1936‐42)と『コドモヱバナシ』(1942‐44)の付記
7章 戦時統制期(1938‐45)に於ける生産者の主体性―金井信生堂、岡本ノート・創立事務所を事例として
終章 近代日本の“絵解きの空間”に於ける子どもと母親の国民化―臣民としての主体性の構築
情報媒体である絵本・絵雑誌、媒介者としての母親、読者である子どもにより構成された受容の場に着目。近代日本の絵本・絵雑誌を分析し、幼年用メディアを介した母子一体の国民化=臣民化の過程を丹念に検証した労作。〈受賞情報〉日本児童文学学会奨励賞(第39回)