[BOOKデータベースより]
明治時代に始まるモスリンの歴史や、今もモスリンに携わる人々の活躍を伝えるページも交えながら、特定非営利活動法人京都古布保存会のコレクションを紹介。「子どものモスリン」の章では動物や乗物など子どもたちが夢見る楽しい柄を、「大人のモスリン」の章では古典を継承しながらもさらに多彩多様になったモスリンの着物・長襦袢柄を四季ごとに掲載している。
子どものモスリン(晴れ着;動物と乗物;子どもの世界;モダンと小柄)
大人のモスリン(春から夏へ;薔薇;よくばりモスリン;秋から冬へ;モダン;吉祥)
柔らかな手触りや染め色のよさから、明治以降もてはやされ、大人気となったモスリン。モスリンのかわいい絵柄を、大正・昭和の子ども着物などから多数紹介。時代の懐かしい香りとともに、歴史や魅力にも触れる。





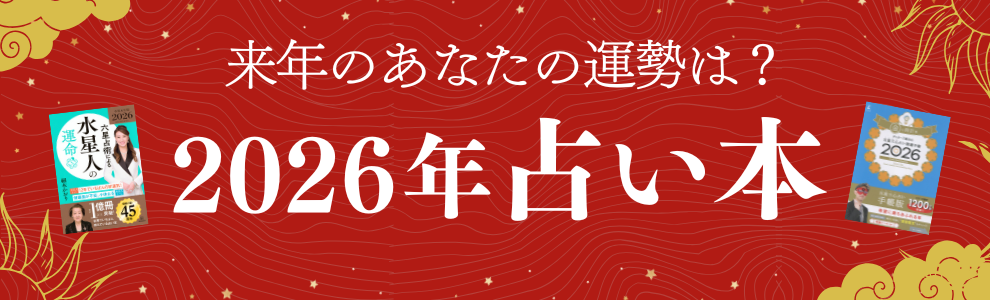

















ウール・モスリンは、化繊が普及する昭和30年代頃まで、日本で大量に生産され、子どもの着物などに使われました。そのため、図柄には今のアニメに通じる楽しくてかわいいものがプリントされています。『明治・大正のかわいい着物モスリン』では、特定非営利活動法人京都古布保存会のコレクションから、モスリンのかわいい図柄を多数紹介いたします。
そもそもモスリンとは単糸で平織りされた布地のことで、その発祥の地と言われるムスリムから名前が由来したと言われています。欧米では産業革命後に綿モスリンが一大ブームとなり、後発のウール・モスリンがそれほど流行しなかったのに対し、日本ではウール・モスリンが明治時代の繊維産業発展期に輸入されるという絶妙のタイミングから、独自の文化として展開しました。さらにウール・モスリンは染料の入りがよく発色も美しいこと、友禅の染め師が染めに参加したこと、絹製品より安価だったことなども、日本で愛され大量に生産される理由です。
特に、子どもの着物や半纏、ちゃんちゃんこには、かわいい動物柄や乗り物柄などの絵柄が考案され、子どもたちの夢を育みました。さらに大人の長襦袢では、着物の下の隠れたおしゃれとして、大胆で大人かわいい柄がバリエーション豊かに生産されました。
本書では、第一部「子どもかわいいモスリン」として、キリンやゾウ、子犬などの動物柄、飛行機や汽船、自動車などの乗り物柄、かわいいキャラクターの子ども柄などを紹介します。
第二部では「大人かわいいモスリン」として、薔薇をはじめとする大胆な花柄や友禅染めの流れからきたと思われる花や鳥などの柄を、四季を交えて紹介するほか、いくつかの柄の布を持ちよってつくられた襦袢を、その楽しい組み合わせから「よくばりモスリン」として掲載します。
同時に、モスリンの歴史や昔モスリンをつくっていた土地の紹介、製造会社についてもコラム立てし、自然に当時の文化や歴史の流れが汲み取れるように構成。さらには現在、モスリンに惹かれて染織に励む方々も紹介、多角的にモスリンの魅力に迫ります。
従来、ウール・モスリンは普段着のイメージが強く、モスリンを主体とした本は今まで一冊も出ていませんでしたので、今回の出版は画期的なモスリン紹介の本となります。