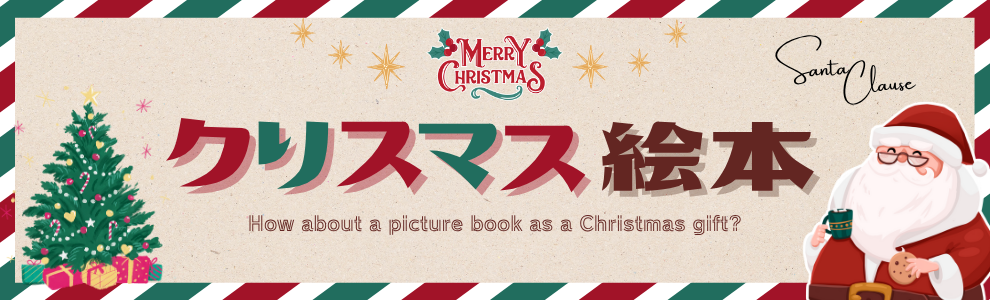[BOOKデータベースより]
東日本大震災の前から、東北の各地では、「道の駅」が地域資源活用の重要な拠点となっていた。その道の駅が、今次の災害では緊急避難所あるいは後方支援機関となり、さらに被災後は復興の拠点として、地域の「灯」、人びとの「希望」であり続けている。本書では、東北地方の11の「道の駅」の奮闘記を通して、その「生産・生活・安全」の拠点としての意義を再確認し、成熟社会における新たな可能性と課題を展望する。
防災拠点としての道の駅
第1部 被災の前線に立つ(宮城県石巻市/震災直後も営業を継続して被災者を支援した「上品の郷」―被災地域において道の駅が果たした役割;福島県相馬市/地震、津波、原発事故の混乱の中で「そうま」―防災拠点としての可能性と課題;岩手県野田村/地域のネットワークが大きな力を発揮した「のだ」―特産品の「塩」と女性起業の力;岩手県山田町/民間主導の道の駅が果たした柔軟な対応「やまだ」―災害対応から産業復興拠点へ;岩手県宮古市田老/津波で崩壊したまちを支えた「たろう」―防災拠点としての役割と課題)
第2部 後方支援に従事(岩手県宮古市川井/流域連携で被災地に物資供給「やまびこ館」―上流の道の駅が下流の沿岸地域の後方支援を行う;岩手県遠野市/休息場所の提供と商品提供に努めた「遠野風の丘」―防災後方支援型都市の一つの機能;宮城県登米市/駅同士の連携で再開を支援した「みなみかた」―発揮された道の駅のネットワーク力)
第3部 被災からの復旧・復興(宮城県気仙沼市/津波被災後、即、仮操業開始「大谷海岸」―被災地域の人びとに応える;岩手県宮古市/被災後一年で仮操業「みやこ」―仮設住宅への移動販売から再開;福島県いわき市/再オープンを果たした「よつくら港」―東北初の「民設民営」型道の駅の再挑戦)
地域を支える道の駅―震災対応からみえてきたこと
地域の「灯」として、震災後、安全確保・物資供給・生産者支援の拠点となった東北の「道の駅」。11駅の奮闘記を通じて、成熟社会における可能性と次なる課題を探る。東日本の人々と共に歩むための緊急報告第3弾。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。