[BOOKデータベースより]
はじめに 子どもの歴史ってなんだろう
大むかしの子ども
子どもたちのすがた
貴族から武士の時代へ
子どもよりも親がだいじ?
子どもが生まれたとき
子どもの夜泣き
もののけを追いはらうおまじない
多かった子どもの死
ぶじに育つことをねがって
ふりわけ髪が肩をすぎたら…
子どもの遊びと歌
わたしのすきな食べもの
女の子が身につけること
男の子が身につけること
大人になる準備
解説と資料
子どもたちは何を食べ、どこに住み、どんな遊びや勉強、働きをしていたのか。子どもの目線で歴史を辿る、今までにない通史。本巻は、平安時代の12歳の少女の目を通して、貴族から武士の時代への変化を見る。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 子ども・大人
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2009年10月発売】
- 子どものためのソーシャルスキルブック
-
価格:1,870円(本体1,700円+税)
【2022年12月発売】
- 日本防災ずかん 1
-
価格:3,630円(本体3,300円+税)
【2024年01月発売】




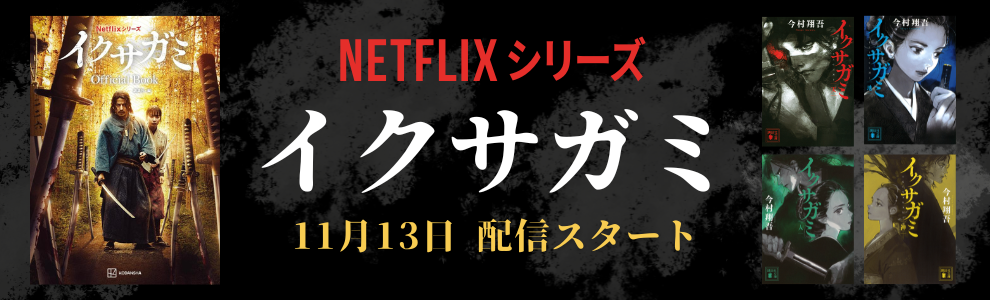











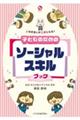











【内容】
日本の歴史のなかで、こどもたちがどのような暮らしをしていたかを、わかりやすく絵本で解説するシリーズ(全5巻)
文:加藤 理 、野上 暁 絵:石井 勉
平安時代ー武士の時代へと変化していくまで。12才くらいの少女の目を通して、こどもの暮らし(仕事、生活、遊び、行事、医療、その他)を描く。
【感想】
始めの方に書かれている話で、かなりショックを受けた。当時は、子どもはよく死んでしまった(医療の不備、飢饉、戦争、病気など)ので、大人の方が大事にされていたという。追いはぎにあった母と子どもが、子どもがおとりになって殺されているうちに、母親が逃げた。それは、「子どもはまた産めばいい」という理由によるからだという。今とはまるで違った考え方で、驚いた。
とにかく、子どもを生むのも命がけ。お産で死ぬ人も多かった。生まれても、小さいうちにコロコロ死んでしまう。病気の原因がわかっていないので、神頼み、おまじないで治そうとした。身分の高い人と、低い人で全然生活の質が違う。庶民の子どもは小さいうちから働いている。勉強ができるのは、稀な事だった…などなど。
時代や生活の違いを知ると、今の生活が本当に楽になっているのがよくわかる。
昔の人は、その時代に対応して、知恵を絞って生きぬいてきて、今の私たちがあることが実感できた。大変な時代を生き抜いて、生き残ってきた歴史。人間はずいぶんしぶとい。この絵本を読んでいて、そんな感慨にひたりました。
絵本自体は、読みやすい文章と、昔の雰囲気が楽しめる素敵な絵。タイムスリップしたような感じです。
年表などの資料も充実しているので、調べものや研究などにも役に立つのではないでしょうか。よく工夫された作品です。(渡”邉恵’里’さん 30代・東京都 )
【情報提供・絵本ナビ】