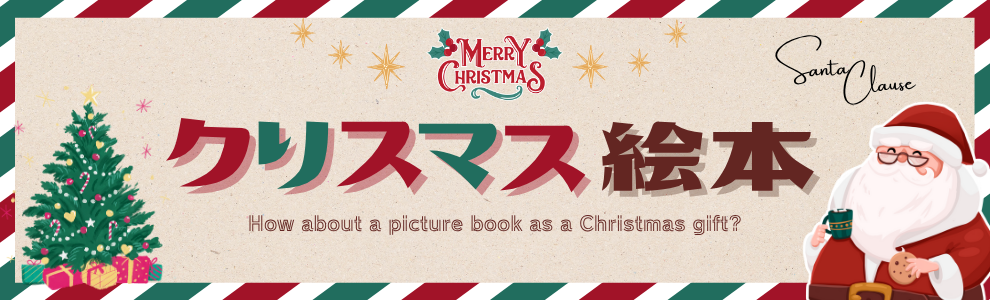[BOOKデータベースより]
大正五年の漱石の死が大正文壇の始まりであったように、昭和二年の芥川龍之介の自死は昭和文壇の始まりであった。そしてその四年前の大正十二年に菊池寛によって創刊された『文藝春秋』が、昭和文壇の形成に大きな役割を果たすことになった。中原中也・小林秀雄・長谷川泰子の「天下の三角関係」、梶井基次郎と宇野千代の恋、「伊豆の踊子」のモデル問題、川端康成の秘めた恋、萩原朔太郎や室生犀星をめぐる女性たちのことなど、昭和初期の文壇を描きだす。
芥川龍之介の自殺(芥川龍之介の支那旅行;江南の旅で宿痾の神経衰弱が顔を出す ほか)
菊池寛、『文藝春秋』を創刊(一高生芥川龍之介と菊池寛;菊池と佐野文夫の同性愛 ほか)
川端康成の恋(天涯孤独な川端康成;「異常を一向異常と感じない」個性 ほか)
中原中也と小林秀雄(富永太郎のマリア;大空詩人永井叔 ほか)
室生犀星と萩原朔太郎(犀川の風に吹かれる;犀星の実父、実母探し ほか)
芥川龍之介の自死は昭和文壇の始まりであった。昭和文壇の形成に大きな役割を果たすことになる「文藝春秋」、中原中也・小林秀雄・長谷川泰子の「天下の三角関係」、川端康成の恋など、昭和初期の文壇を描きだす。