- 寺社と芸能の中世
-
- 価格
- 880円(本体800円+税)
- 発行年月
- 2009年04月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784634546929
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 尋尊
-
価格:2,530円(本体2,300円+税)
【2021年10月発売】
- 全集日本の歴史 第7巻
-
価格:2,640円(本体2,400円+税)
【2008年06月発売】
- 武蔵の武士団
-
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2020年02月発売】




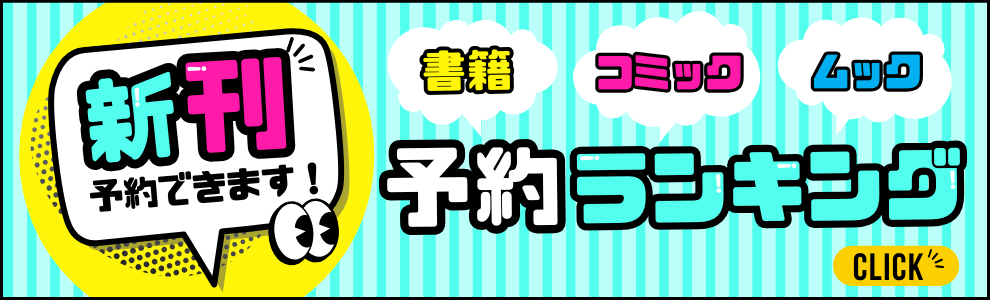


















[BOOKデータベースより]
寺院や神社の境内には、清澄で落ち着いた空気が流れている。仏堂や社殿など、多くの建築が歳月をへてしぶい色をみせていることも、あの特有の雰囲気をつくりだしているだろう。しかし、かつて寺社の境内は、もっとにぎやかで楽しい場所だったかもしれないのである。法会や祭礼の日はもちろん、そうでないときにも僧侶や神官たちはしばしば田楽・延年・猿楽などの芸能を楽しんだ。多くの芸能者たちが寺社に出入りし、僧や神官、美しく装った稚児たちが芸能を鑑賞し、みずから演じてもいた。中世の寺社は、劇場でもあった。
寺社・もうひとつの中世社会
[日販商品データベースより]1 田楽・邪気払いの呪法(永長の大田楽;武家と田楽 ほか)
2 延年・僧と稚児の競演(遐齢延年;開会式と音楽会 ほか)
3 猿楽・四座と寺社の葛藤(田楽から猿楽へ;室町時代の薪猿楽 ほか)
中世への回路
清澄な空気が流れる寺院や神社の境内。しかし、中世の寺社は多くの芸能者たちが出入りする劇場だった。そこで行われていた田楽・猿楽・延年などの芸能を通して、寺社や政治・社会の動向を歴史学的に考察する。