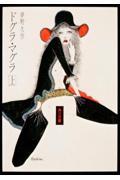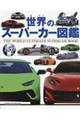[日販商品データベースより]
「ドグラ・マグラ」は、昭和10年1500枚の書き下ろし作品として出版され、読書界の大きな話題を呼んだが、常人の頭では考えられぬ、余りに奇妙な内容のため、毀誉褒貶が相半ばし、今日にいたるも変わらない。〈これを書くために生きてきた〉と著者みずから語り、10余年の歳月をかけた推敲によって完成された内容は、著者の思想、知識を集大成する。これを読む者は一度は精神に異常をきたすと伝えられる、一大奇書。
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。

ユーザーレビュー (4件、平均スコア:5)
レビューを評価するにはログインが必要です。
この商品に対するあなたのレビューを投稿することができます。
-
HonyaClub.comアンケート





-
「おすすめ夏の文庫2014」レビューコメント
昨今の事件の犯人の心理が理解できないという方へ事件など起こさなくても人はここまで怪奇なる物だと理解することでしょう(tekeriri/男性/30代)
-
HonyaClub.comアンケート





-
「怖い本」レビューコメント
今読んでも理解できそうで、できない。(ボリス/男性/30代)
-
HonyaClub.comアンケート





-
「オススメの夏の文庫100冊」レビューコメント
もうわけわからない本です。夢野久作の代表作で日本探偵小説三大奇書と言われてます。う〜んでも探偵小説じゃないんだけどなぁ。ぜひ一度は夢野ワールドへ。(おっさん/男性/40代)
-
せみまる





-
日本三大奇書
正確に言うと、角川文庫版ではなく筑摩書房の『 夢野久作全集〈9〉 』を底本とした青空文庫版をpdf化しSONYの電子書籍端末Readerで読了しての感想です。
まず、記憶喪失の語り手が目覚めるというシーンから物語が始まります。そして、語り手が医師から「心理遺伝」や「骨相学」などの説明を受けるなど、そういった題材が奇想小説の由来かと思いきやさにあらず。主人公が精神病理学者の遺した書類を読み始めてから、本書はメタフィクションの様相を帯びてきます。すなわち、論文や警察の調書・新聞記事などが一人称の語り手の目を通して読者に提出されるのです。
就中、ある登場人物の先祖について擬古文調で語られるくだりや、そのまた先祖の始皇帝の時代の中国における物語が語られるところなど、小説内伝奇小説といった風情。そこかしこにコメディの雰囲気もあり、なんだか大真面目に冗談を言われているような気さえします。
そして、何より素晴らしいのはその文章のテンポの良さ・心地よさ。落語とか講談とか真面目に聴いたことはないですが、あの日本語の感覚に近いと感じられます。著者は謡曲喜多流の教授をしていたことがあるらしいから、そのあたりの影響もあるにちがいないでしょう。
と思ったのが中盤終了までで、それ以降はネタバレとなりそうだから詳述は控えておきますが、読み終えてみると、なるほど三大奇書といわれるのが不思議じゃない迷宮感覚に襲われます。さまざまな小説形式やアイデアのごった煮。そのなかに得も言われぬ秩序があるのが不思議な小説です。
75年前に出版された作品が、21世紀の最初の10年紀を過ぎた今でも文庫で読めるということ、そしておそらくは売れ続けているであろうことには驚嘆させられます。ちなみに、本書を世に問うた翌年に著者は逝去したとのこと。