[BOOKデータベースより]
李白、杜甫、陶淵明、蘇東坡―四千年の歴史が生んだ名詩の舞台へ。細川流「中国歴史紀行集」。
孔子―逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎かず(北京市・故宮)
老子―足るを知る者は富む(河南省・霊宝市函谷関)
『史記』―桃李言わざれども、下自ずから蹊を成す(陝西省・興平市)
『三国志』―星落つ秋風五丈原(陝西省・宝鶏市五丈原)
『三国志』―語るに言少なく、善く人に下り、喜怒を色に形わさず(四川省・成都市武侯祠)
曹丕―文章は経国の大業、不朽の盛事(陝西省・西安市碑林博物館)
王羲之―高爽にして常流に類せず(浙江省・紹興市戒珠寺)
陶淵明―帰りなんいざ(江西省・九江県廬山)
陶淵明―廬を結んで人境に在り(江西省・九江県廬山)
達磨―不識(江蘇省・南京市石頭城)〔ほか〕
週刊文春に四年間にわたって連載された細川元首相の旅行記の単行本化。歴史上の人物の名言をテーマに日本全国を歩いた『ことばを旅する』の第二弾、今度は中国編です。
李白、杜甫、王維、陶淵明、白楽天、文天祥??。細川さんが幼少の頃から親しんできた漢詩の文人たちが残した名言名句を手がかりに、舞台となった地を訪ねました。
たとえば、杜甫の「国破れて山河あり」の舞台となった長安を旅し、唐の詩人たちが活躍した往時の都を偲びます。また、陶淵明の「帰りなん いざ」に導かれ、名勝を謳われた廬山へ。さらには、蘇東坡が「人生夢の如し」と謳った古戦場である赤壁を訪れ、『三国志』の時代に思いを馳せる――。
なかには達磨や玄奘といった僧侶や、王羲之や八大山人のような書家や画家も登場しますが、それも細川氏が考える「詩心(うたごころ)」を感じられる人選なのです。
中国全土を巡り、四十八話をつづった細川護煕流「中国歴史紀行集」。旅愁を誘う撮り下ろし写真や、筆者自ら旅の印象を描いた絵画や書もふんだんに盛り込みました。



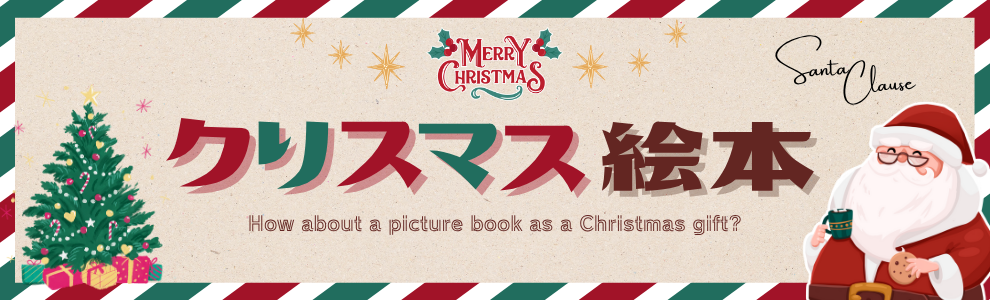










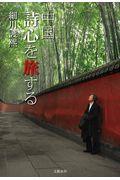










細川元首相が幼少時から親しんできた李白や杜甫、陶淵明など漢詩の名文・名句が生まれた場所を中国全土に訪ねた紀行集。写真も満載。