- 「いろは」の十九世紀
-
文字と教育の文化史
ブックレット〈書物をひらく〉 26
- 価格
- 1,100円(本体1,000円+税)
- 発行年月
- 2022年03月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784582364668
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 英語のルーツ
-
価格:1,430円(本体1,300円+税)
【2026年02月発売】
- オールドメディアのラスボス NHK解体新書
-
価格:1,210円(本体1,100円+税)
【2026年03月発売】
- 社会は、静かにあなたを「呪う」
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2025年08月発売】


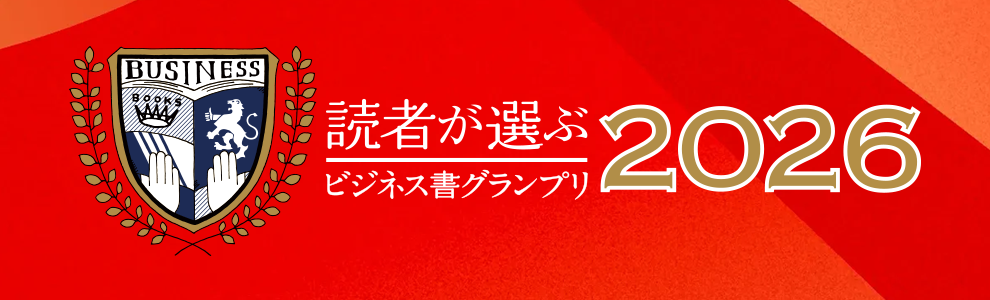

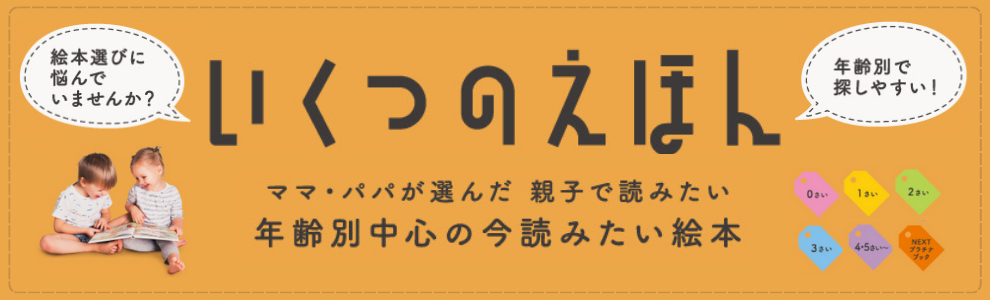
























[BOOKデータベースより]
十九世紀がはじまる頃、寺子屋は盛んになり、ひろく庶民の子弟が読み書きの習得に励むようになる。この世紀の終わりに、小学校教育が制度化され、五十音図に切り替わるまで、文字学習の出発点は「いろは」。「いろは」の世紀に、文字教育はどのように営まれたか。外国人の東洋語理解や出版の変化も絡めながら多角的に描き出す言語・教育文化史。
1 「いろは」とはどういうものか
[日販商品データベースより]2 寺子屋の「いろは」(入門としての「いろは」;往来物で学ぶ;寺子屋から学問・芸道の世界へ)
3 西洋人の「いろは」(ロニー―仮名活字の製作者;ヘボン―日本宣教と辞書;チェンバレン―日本学の大成者)
4 小学校の文字学習(「いろは」から「五十音図」へ;小学校で漢字を学ぶ;近代的な小学校へ;木版本から活字本へ―文字の統一)
5 「いろは」の十九世紀
広範な庶民の子女が寺子屋に通いはじめてから近代小学教育が確立するまで、「いろは」が文字教育の中心だった百年を、外国人の日本語学、印刷技術などの視角も含め描き出す。