この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 顧客の数だけ、見ればいい
-
価格:1,815円(本体1,650円+税)
【2024年10月発売】
- 会社は「本」で強くなる
-
価格:1,870円(本体1,700円+税)
【2025年10月発売】
- 組織をダメにするのは誰か? 職場の問題解決入門
-
価格:1,738円(本体1,580円+税)
【2025年02月発売】
- 中小企業診断士 はじめての診断報告書
-
価格:2,640円(本体2,400円+税)
【2025年12月発売】


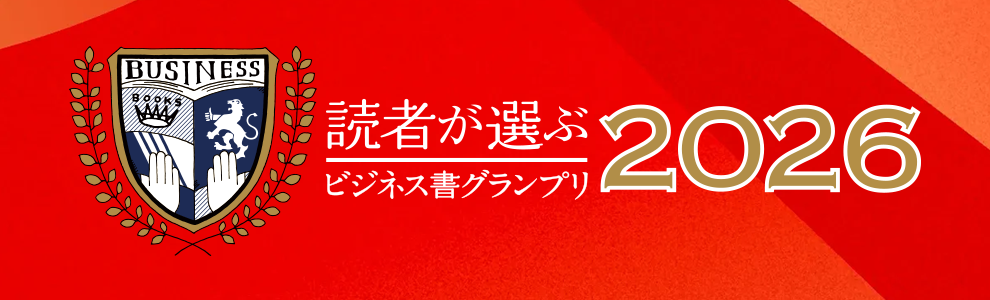

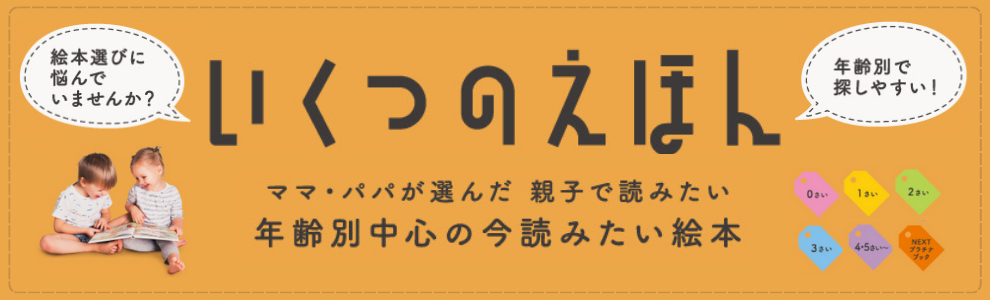





















[BOOKデータベースより]
1 今、講ずるべき経営の打ち手(日本企業の強みと弱みとは;現場の本質とは何か ほか)
[日販商品データベースより]2 経営改革の実践者たち(ファインネクス―年商60億円のグローバルニッチトップが挑んだ興隆と危機;TOA―地産地消ビジネス企業が成し遂げた世界共通のマネジメント ほか)
3 データ活用の実践者たち(阪急阪神ホールディングス―「都市データ」クラスの大規模データ活用への挑戦;塩野義製薬―グローバル展開を目指す、ヘルスケア領域のデータ活用 ほか)
4 社長が語る経営の本質―Dialogue 萩原工業代表取締役社長 浅野和志氏×生方製作所代表取締役社長 生方眞之介氏(ニッチトップが手掛けるソリューションの数々;経営の本質は何十年も変わっていない ほか)
5 事例に学ぶ意義(個社による情報収集の限界;なぜ事例が欲しいのか ほか)
◆部分最適の先にある「全体最適」へ
事業計画や会議の議事録、在庫管理、決算処理、さらには従業員の勤怠管理まで、いまや企業活動のすべてがデジタル化されている。
しかしデジタル化による効果は、多くの場合、「時短になった」などという表面的な部分にとどまっている。
言うなれば「部分最適」である。
デジタル化によって作業効率や生産性が高められたのであれば、「部門間の連携が強化され、新たな企業価値創造につながった」という経営効果が現れてしかるべきだ。
それなのになぜ日本企業の多くは「部分最適」にとどまり、「全体最適」できないのだろうか。
そこには依然として、「テクノロジーは効率化の手段」と見なす企業風土があるのではないか?
本書ではテクノロジーによって経営効果を高めるためのアプローチを、実際の企業での取り組みを例に紹介する。
「もしあなたが、ITに使われる人でなく、使いこなす人になりたいなら」――『経営戦略全史』著者・三谷宏治氏推薦!!