- ���o�̐l�ފw
-
���q���k�́u�����v�ƊJ���x��
���E�v�z��
���c�f���@�V�{�����q�@- ���i
- 3,850�~�i�{��3,500�~�{�Łj
- ���s�N��
- 2022�N06��
- ���^
- �`�T
- ISBN
- 9784790717683

���[�U�[���r���[
���̏��i�Ɋ�ꂽ�J�X�^�}�[���r���[�͂܂�����܂���B
���r���[��]������ɂ����O�C�����K�v�ł��B
���̏��i�ɑ��邠�Ȃ��̃��r���[�𓊍e���邱�Ƃ��ł��܂��B


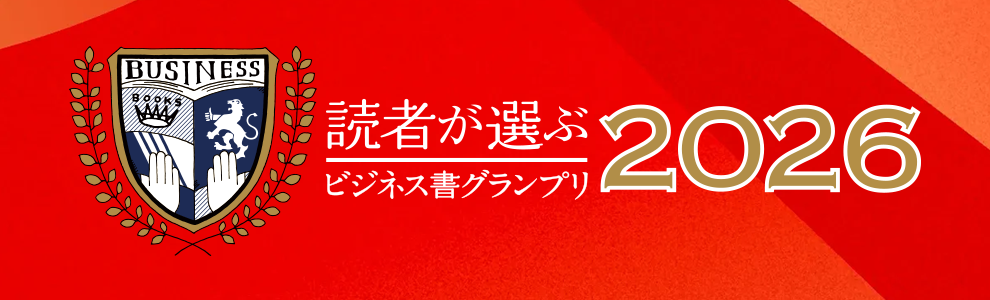

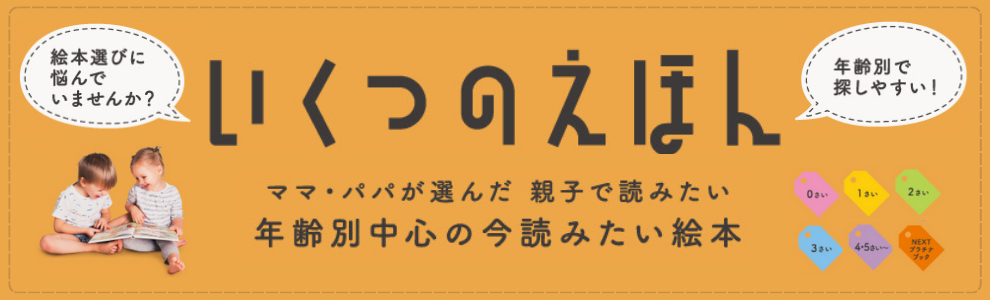
















[BOOK�f�[�^�x�[�X���]
�g�����h�̐g�̓I�Ȑ������ۂł��邾���ł͂Ȃ��A���܂��܂ȗ̈�̐[�������Ɋւ��A���W�r�㍑�����A���邢�͓��{�����̂��̂ł͂Ȃ��n�����łȂ����Ă���B
���_
[���̏��i�f�[�^�x�[�X���]��P���@�O���[�o���ȊJ���ۑ�ƂȂ������o�i���ۊJ���̖ڕW�ƂȂ������o�q���Ώ��\�l�g�l�Ƃ́G���ۊJ���̑ΏۂƂȂ������o�̕����l�ފw�I�ۑ�j
��Q���@�e�n��̃��[�J���ȕ����ƌ��o�Ώ��i�p�v�A�j���[�M�j�A�Ĕ��_�k���A�x�����̌��o�Ώ��ƊJ���x���̂������G�C���h�l�V�A�_�����̏��q���w���͂ǂ̂悤�Ɍ��o�Ώ����Ă���̂��\�w�Z����ƃC�X���[���K�͂ɒ��ڂ��āG�J���{�W�A�_���Љ�ɐ����鏗���Ɓu���فv�̈Ӗ��\���o�̌o���Ǝ��H�ɒ��ڂ��ā@�ق��j
��R���@�l�g�l�x���̎��H�ɂނ��āi���[�J���ȕ������猩����J�����H�ւ̎����j
�����̌��o���߂�����́C���W�r�㍑�����ŋN���Ă�����ł͂Ȃ��B
�킽�������̐g�߂Ȃ��܂��܂ȂƂ���ŁA�n���ɋN�����Đ����p�i�����荢��ȏ����邱�Ƃɑ��ď��������������グ�Ă���B���� �gperiod poverty�i�����̕n���j�h�Ƃ����\�����C�M���X�̃}�X�R�~���p���Ĉȗ��C��ŊJ���gperiod equity�i�����̕������j�h�����߂邤�������e�n�ɍL�����Ă���B�܂��A�r�㍑�ƌĂ��n��ł́C�W�F���_�[�����C���q����̌���C�q������ɂ����鏗���z���Ȃǂ̊ϓ_���猎�o�Ώ��͊J���x���̑ΏۂƂ���A�n��ɌŗL�̕����I���K�⌎�o�ς́A���E�I�Ȃ��˂�̂Ȃ��ŗh�炢�ł���B
�@�{���ł́C���o���߂��鍑�ۊJ���̓������܂��������C�e�n�̃��[�J���ȕ����ƌ��o�Ώ��̌�����Ƃ炦��B
����ɁA�e�n�̃t�B�[���h���[�N�œ����������ƂɌ��n�̏��Ă��˂��ɕ��͂��A�e�n����r���邱�ƂŁA���ۊJ���̌���ł̎x���ɑ��鎦���𒊏o���邱�Ƃ����݂�B
���{���̍\��
����T��
�@���ۊJ���ɂ����Č��o�Ώ����Ȃ����ڂ𗁂сC�x�����K�v���ƔF�������悤�ɂȂ����̂����ڏq�A��̓I�Ȏx���̊T�v�������B
��1�́F�u���o�q���Ώ��v�iMHM�j�̌n���Ɠ����C�r�㍑��ΏۂɍL����u�J���̔g�v�̍��ۓI�ȕ������C��U���̎���ւƓǂݐi�߂Ă��������O�m���Ƃ��āB
��2�́F���o�̕����I���ʂ̌����~�ς̑��������l�ފw�̂Ȃ��ŁC���o�ɂ��Ăǂ̂悤�Ȍ���������܂łȂ���Ă����̂���U��Ԃ�B
����U��
�@���E�̊e�n��ɂ����錎�o���߂��郍�[�J���ȕ����Ə��q���k�����̌��o�Ώ��ɂ��Ă̎����`���Ă����B�\�\�����m�ɖʂ��ԓ��̏����쑤�Ɉʒu����p�v�A�j���[�M�j�A�i��3�́j���琼�������ăC���h�l�V�A�i��4�́j�C�J���{�W�A�i��5�́j�C�C���h�i��6�́j�C�C���h�m��n���ē��A�t���J�̃P�j�A�ƃE�K���_�i��7�́j�C����ɃE�K���_�̕ʒn��i��8�́j�C�吼�m���z�������Ẵj�J���O�A�i��9�́j�C�Ō�ɑ����m�𐼂֓��{�i��10�́j�܂Ŗ߂�C�e�n��̎�����݂Ă����B
����V��
���o�Ɋւ���J���x�������{����ۂɒn��̕����œ��ɒ��ӂ��ׂ��_���C��2���̎�����l�@�����o����B�܂����^�����Ƃ��āC�����̎��_�Ō���8�����̑Ώےn��̊T�v���}�g���b�N�X�ɂ��Čf�ڂ��Ă���B
���R����
���o���W���鑽�l�ȑ��ʂɂ��āC�L���g�s�b�N���W�߁C�e�͂̊Ԃɂ͂��B���ʓI�Ȍ��ۂł��錎�o�ɂ��āC���܂��܂Ȋp�x����l���邽�߂́A���������Ƃ��āB