- バリュエーションの理論と実務
-
日経BPM(日本経済新聞出版本部) 日経BPマーケティング
鈴木一功 田中亘- 価格
- 3,960円(本体3,600円+税)
- 発行年月
- 2021年12月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784532135232
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- わたしたちのエンゲージメント実践書
-
価格:2,750円(本体2,500円+税)
【2025年03月発売】
- オペレーショナル・エクセレンス 業務改革(BPR)の理論と実践
-
価格:1,958円(本体1,780円+税)
【2024年11月発売】
- 企業を高めるブランド戦略
-
価格:990円(本体900円+税)
【2002年09月発売】
- 先義後利の経営
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2024年07月発売】
- 実践危機管理広報 改訂版
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2011年02月発売】


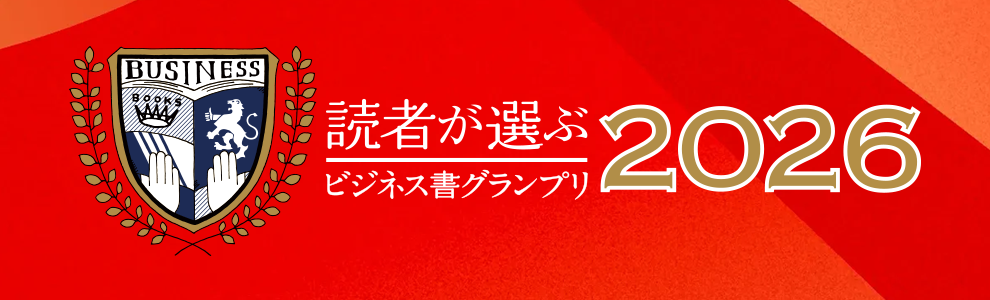

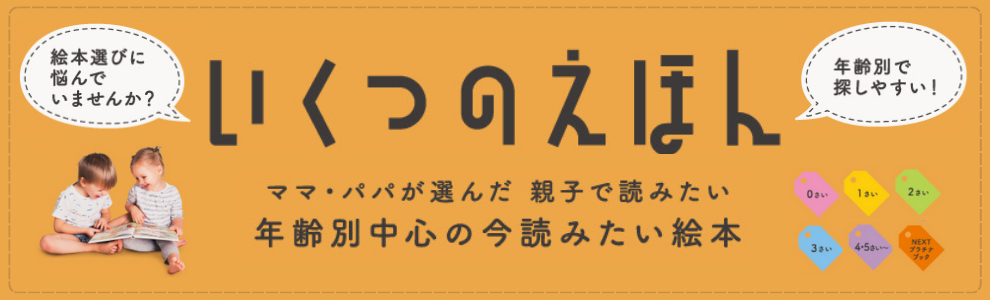
























[BOOKデータベースより]
実務の現場において、実務家の一部が自分たちに都合の良い結論を導くために、背景となる理論の一部をつまみ食いして使っており、企業価値評価実務の全体を通してみると、必ずしも理論的一貫性がとれていないのではないかという懸念がある。本書は、このような懸念を踏まえて、その背景となる理論の前提との整合性や、実務上の運用において評価者に許容される裁量の範囲について、法学、経済学、金融経済学、会計学の研究者に加えて、企業の合併・買収(M&A)の専門家である法務分野、および実際の企業価値評価に携わる実務家が、裁判などで争われているような論点を取り上げ、そこで当事者が引用している理論の妥当性や問題点を検証するものである。
第1部 日本のバリュエーションをめぐる課題(M&Aやファイナンスにおけるバリュエーションの実務と課題;会社裁判におけるバリュエーションの課題)
[日販商品データベースより]第2部 M&Aにおけるバリュエーションの実務(M&Aのプロセスとバリュエーション;わが国のM&Aにおけるバリュエーションの実務)
第3部 会社裁判における問題点(日本の会社裁判におけるバリュエーションに関する法的論点;米国・デラウェア州の会社裁判におけるバリュエーションの争点)
第4部 バリュエーションの理論:インカム・アプローチ関連(インカム・アプローチの基礎;特殊なバリュエーションに関する理論 ほか)
第5部 バリュエーションの理論:インカム・アプローチ以外の手法(マーケット・アプローチ;コスト・アプローチ ほか)
バリュエーション(企業価値評価)とは、特定の会社自体の価値やその株式の価値を算出する手法。日本にはM&Aが盛んになり始めた20世紀末に導入され、瞬く間に定着しました。M&A、TOB、事業承継、事業分割において不可欠なデータを提供するバリュエーションですが、つぎはぎで導入されたこと、司法の理解が追いつかなかったこともあって様々な面で解釈の誤り、恣意的な運用といった歪みが生じています。最高裁の決定も実務の慣行とかけ離れたものが散見され、実務家は最高裁に振り回されている状況にあるのです。
例えば、アートネイチャーとJCOMの判決内容は結論部分が類似していて、算定された価格について裁判所は判断しないというスタンスをとっています。そのため、当事者にとっては、自己に都合の良い株式価値算定書が入手できれば、有利な判決を受けやすいという状況に現状はなりつつあります。このスタンスが踏襲されてしまうと、市場メカニズムが十分に機能せず、日本のガラパゴス化は不可避です。実務家は企業価値を計算するだけでは済まされない。どこが落とし穴になりかねないのかを理解する必要があるのです。
バリュエーションが裁判で争点となる場面としては、次の4つが想定されます。
(1)M&Aにおいて反対株主が株式の買い取り請求権を行使して「公正な価格」で買い取ることを会社に請求する場面
(2)株式ファイナンスにおいて発行価額が特に低い時に株主総会の特別決議を経る必要がある場面
(3)非公開会社の譲渡制限株式について株主が譲渡承認請求をする場面
(4)新株予約権の評価
これらは、大企業のみならず中小企業にも生じうるものです。本書は、企業価値評価の実務家、ファイナンス研究家、会社法研究家がタッグを組んで、実践的な知識の向上を図り、司法の歪みを正し、国際的に標準の解釈を示す問題提起の書。執筆者の多くは、様々な裁判で意見書を求められており、日本の特異な状況に危機感を抱いています。
バリュエーションそのもの解説書は、入門レベルから専門書まで数多く刊行されていますが、日本においてどのような問題が存在し、実務上何に注意すべきかといった観点からの解説はなされていません。バリュエーションは目次にあるように非常に幅広い分野をカバーしているため、単独の筆者では問題提起を含んだ解説は不可能です。