- 大江戸まちづくりの不思議と謎
-
古地図でわかる!
じっぴコンパクト新書 373
- 価格
- 1,078円(本体980円+税)
- 発行年月
- 2020年02月
- 判型
- 新書
- ISBN
- 9784408339023
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 浮世絵でわかる!江戸っ子の十二刻
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2025年06月発売】
- 浮世絵でわかる!江戸っ子の二十四時間
-
価格:1,298円(本体1,180円+税)
【2014年06月発売】
- 「忠臣蔵」の決算書
-
価格:814円(本体740円+税)
【2012年11月発売】
- 漫画版日本の歴史 10
-
価格:660円(本体600円+税)
【2018年12月発売】


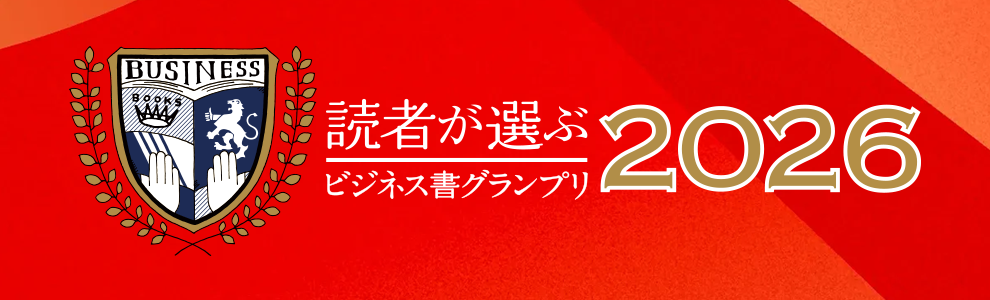

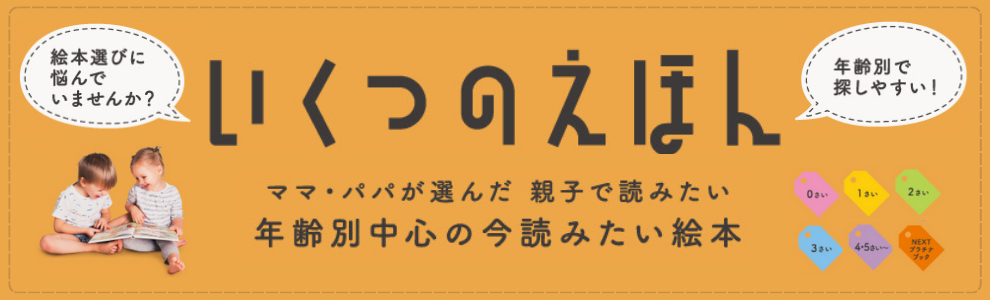









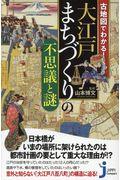







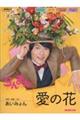





[BOOKデータベースより]
慶長8年(1603)、江戸に幕府を開いた徳川家康が、江戸城を中心とした本格的なまちづくりに着手した。以降、たび重なる「天下普請」によって都市インフラが整備され、「大江戸八百八町」と呼ばれる巨大都市が完成した。その当時の様子を知るよすがとなるのが、江戸時代に制作された古地図である。江戸のまちはどのような都市計画によって築かれたのか、人々はどのような生活を営んでいたのか。古地図をもとにして、江戸のまちづくりを解説する。
第1章 古地図でたどる大江戸三〇〇年のまちづくり(江戸をつくる 家康・秀忠・家光の徳川三代が巨大都市・江戸の基盤を築く;城のしくみ1 将軍とその家族が住んだ江戸城、内部はいったいどうなっていた? ほか)
[日販商品データベースより]第2章 古地図でわかるお江戸のしくみとルール(江戸の宿場 江戸近郊に置かれた宿場町は江戸っ子の遊興の場でもあった!;江戸の大寺院 江戸城の鬼門の方角に二つの大寺院が配された意図 ほか)
第3章 古地図で読み解く江戸の暮らし―武士編(将軍の一日 武家政権のトップとして日本を治めた将軍はどんな生活を送っていた?;将軍の輿入り 将軍の正室が暮らした大奥にはどんな部屋があった? ほか)
第4章 古地図で読み解く江戸の暮らし―町人編(江戸の町人地 通りを挟んで構成された「両側町」、町の基本単位は「向こう三軒両隣り」;職人町と商人町 城下町づくりに貢献した御用職人と御用商人 ほか)
武家屋敷はなぜ移転した? 寺町再構築の意図は? 市場の設置場所の意味は? 江戸期の街づくりからいまの東京の街の構造をひもとく。