[BOOKデータベースより]
日本人の苗字の起源は、弥生時代に韓半島から渡来した人びとが祖国の地名や種族名、職能集団名を古代朝鮮語や大和ことばにあててあだ名で呼んで私称したことに始まる。縄文人は生活に必要な範囲でそれぞれ名前を付けて呼んでいたが、渡来人の鉱山・鍛冶技術や稲作技術を吸収するとともに大和ことばで自分たちのあだ名を苗字として名乗ったのである。『埼玉苗字辞典』をベースに旧説を覆し、日本人の苗字の起源を新たな視点で解読する。
第1章 渡来の人々(中国江南の呉越族倭人;朝鮮半島の呉越族倭人 ほか)
第2章 古代苗字の一〇〇大姓(渡来の様子;あだ名の私称 ほか)
第3章 部民の姓氏と苗字の違い(村と郷;孔王部 ほか)
第4章 武士の名字と苗字の違い(名字と苗字;苗字の所見 ほか)
日本人の苗字の起源は、韓半島から渡来した人々が祖国の地名や種族名を大和ことばなどにあてて、あだ名として私称したことに始まる。『埼玉苗字辞典』を基に旧説を覆し、日本人の苗字の起源を新視点で解読する。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 箱式石棺
-
価格:22,000円(本体20,000円+税)
【2015年12月発売】
- ジオ・ヒストリア 世界史上の偶然は、地球規模の必然だった!
-
価格:1,760円(本体1,600円+税)
【2022年11月発売】


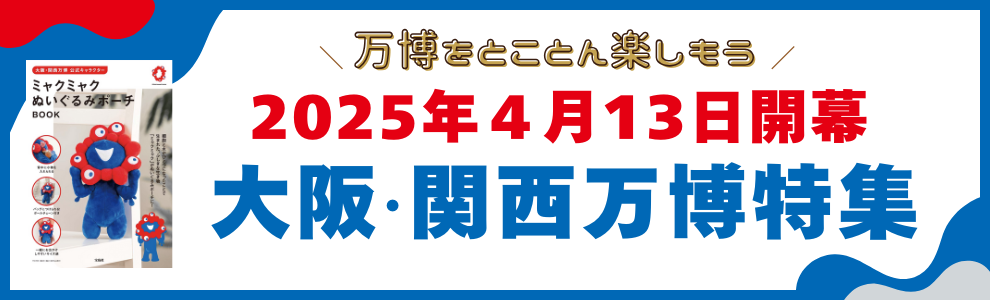
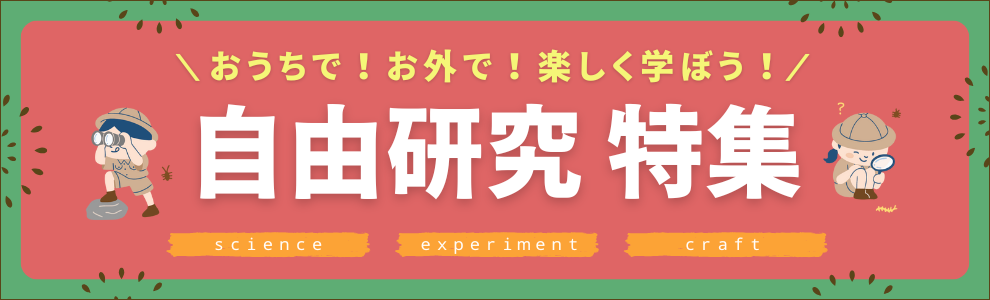
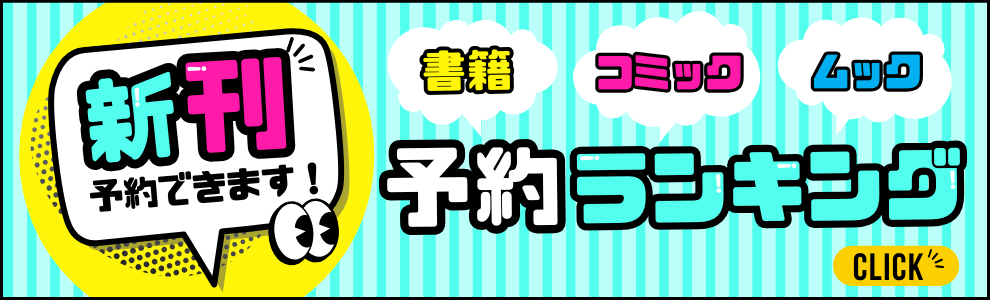
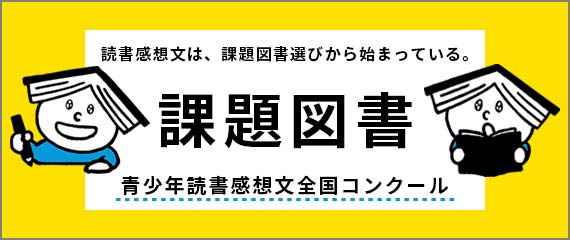














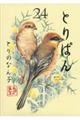



[商品紹介]
そんな気がする!
「古代の人びとは苗字をあだ名として私称していた!!」従来、「佐藤」という姓は、官職名の左衛門尉の「左」と、藤原の「藤」とから発生した、という説、あるいは、栃木県佐野から取った「佐」と藤原の「藤」からきたという説があるそうです。しかし、この本ではちょっと違って、朝鮮の金海(古名を砂羅)・梁山(古名を沙羅)から来た人々が、「砂」=「沙」=「佐」と、「羅」=「加羅」→「唐(から)」→「藤」と読み替えたて自称したことが始まりだというのです。「苗字」そのものの由来