[BOOKデータベースより]
曲尺の種類と使い方、軒回りの種類と名称、勾配の基礎知識、折り紙でつくる各種模型。実際に1本の曲尺(指金)から、墨付けができるようになる!入門者必見。
写真で見る軒回り 千本釈迦堂 大報恩寺
写真で見る軒回り 相国寺 法堂
一軒隅製作で学ぶ規矩術実習の現場
規矩術で使われる道具について
曲尺という道具とその周辺
規矩術
曲尺(指矩)
折り紙で学ぶ規矩術
伝統の大工の技「規矩術」。曲尺を使って勾配を求める複雑な技術論を、折り紙で模型を作りながらわかりやすく解説。実際に1本の曲尺から、墨付けができるようになる。規矩術の考え方を根本から理解するための教本。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- これで完璧!マンション大規模修繕 最新増補改訂版
-
価格:3,300円(本体3,000円+税)
【2025年03月発売】
- 木造住宅 設計監理のステップアップ講座
-
価格:3,080円(本体2,800円+税)
【2025年03月発売】
- 明解和洋さしがねの使い方 第6版
-
価格:2,750円(本体2,500円+税)
【2025年01月発売】
- 木工手道具 墨付けと木組みの技法
-
価格:3,850円(本体3,500円+税)
【2023年12月発売】
- 鑿大全 第3版
-
価格:4,400円(本体4,000円+税)
【2023年12月発売】




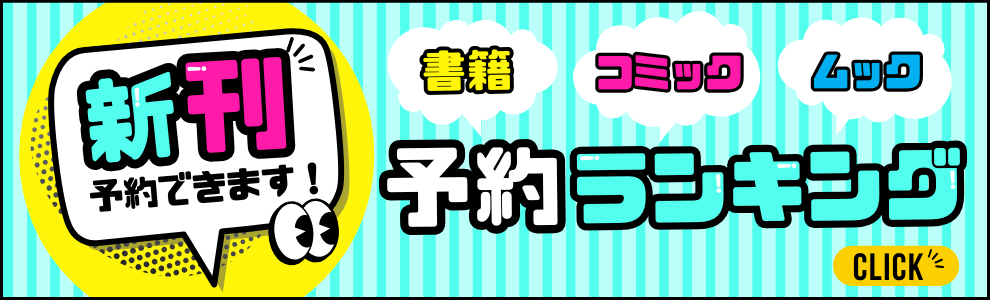












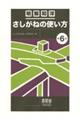







古建築で使われてきた「規矩術」の技法。それは主に社寺などの軒回りの構造に見ることができます。それらの構造を踏まえ、「規矩術」の目的を知ることから、実際の軒回り作りを巻頭のカラー写真で解説していきます。「規矩術」の考え方や使い方は、折り紙で模型を作りながら、その構造を理解し、実際に1本の曲尺(さしがね)から、墨付けができるようになるまでを解説していきます。監修は近世規矩術の選定保存技術保持者である持田武夫氏が担当。氏が推奨する折り紙模型を使った規矩術の学習方法を用い、規矩術の考え方を根本から理解するための教本。
写真で見る曲尺の種類と歴史
古建築を担う職人たち
写真で見る軒回りの種類と名称
規矩術とは
規矩の歴史
軒回りの解説
曲尺の解説ー特徴と使い方
勾配の基礎知識
勾配の応用と実践
折り紙でつくる各種模型…など