[BOOKデータベースより]
運ぶのは遺体だけじゃない。国境を越え、“魂”を家族のもとへ送り届けるプロフェッショナルたち。2012年第10回開高健ノンフィクション賞受賞。
遺体ビジネス
取材の端緒
死を扱う会社
遺族
新入社員
「国際霊柩送還」とはなにか
創業者
ドライバー
取材者
二代目
母
親親父
忘れ去られるべき人
おわりに
国境を越えて遺体を家族のもとへ送り届けるのが国際霊柩送還士の仕事。日本初の専門会社で働く人々と遺族の取材を通して、著者は人が人を弔うことの意味を知る。〈受賞情報〉開高健ノンフィクション賞(第10回)
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 匂いに呼ばれて
-
価格:2,200円(本体2,000円+税)
【2025年10月発売】
- 海の魚鱗宮
-
価格:902円(本体820円+税)
【2023年10月発売】
- 夜明けを待つ
-
価格:1,980円(本体1,800円+税)
【2023年11月発売】
- エンジェルフライト
-
価格:682円(本体620円+税)
【2014年11月発売】
- 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている
-
価格:990円(本体900円+税)
【2017年02月発売】

ユーザーレビュー (1件、平均スコア:5)
レビューを評価するにはログインが必要です。
この商品に対するあなたのレビューを投稿することができます。
-
Tucker





-
「死」と向き合う
海外で亡くなった日本人、日本で亡くなった外国人の遺体を家族の元に返す「国際霊柩送還」専門会社エアハース・インターナショナルの人々に密着したドキュメンタリー。
その業務の性格上、どうしてもきつい表現が多いので、万人に勧められる本ではないと思う。
その点を除いても(海外で死亡してしまうかは別にして)「死」は誰もが必ず経験(?)することだけに、そう何度も読み返せるものではない、と感じた。
(内容が不快という訳でなく、誰にでも起こる事で痛すぎるから)
以前読んだ、上野顕太郎の「さよならもいわずに」(ビームコミックス)を思い出した。
こちらも同じ理由で、未だに読み返す「勇気」が持てない。
エンバーミング(防腐処理)の是非や海外の遺体搬送ビジネスの「闇」にも触れているが、「死」とどう向き合うか、という話がメイン。
人は死んだ後、いつから「死者」になるのだろう?
客観的には「心臓が止まった時から」なのだろうが、残された側にとってはどうなのだろう?
理屈では、もうその人はそこにいない、というのは分かるが、どうしてもまだ何かが残っているように思える。
と言うより思いたいのかもしれない。
前述の「さよならもいわずに」にも葬儀社の人に「何か形があった方が送り手の方が安心するものだ」と言われる件があったのを思い出した。
そのため、遺体や儀式という「形」が必要なのだろう。
そして、死者と向き合いやすくしたのが「エンバーミング」なのかもしれない。
人間の体を破壊する力を持つ技術が発達したという事と二人三脚ではあるだろうが・・・。
おそらく世界中に「葬式」という儀式があるのは、死んだ人のためであると同時に、残された側のためでもあるのだろう。
「死」を納得し、受け入れやすくするために。




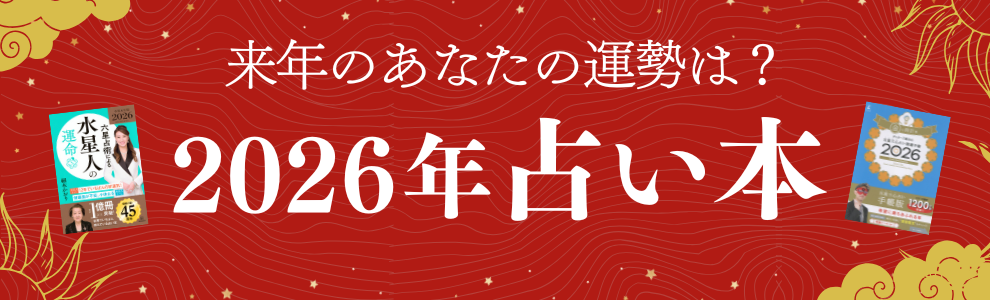






















ママが遺体にキスできるように。それが彼らの仕事。国境を越えて遺体を家族のもとへ送り届けるのが国際霊柩送還士の仕事。日本初の専門会社で働く人々と遺族の取材を通して、筆者は人が人を弔うことの意味、日本人としての「死」の捉え方を知る。