[BOOKデータベースより]
考古学という、とても古い時代のことを調べる学問があります。出土品や石のかけらなど、ふつうの人には何の価値もないような古いものや、遺跡などから、過去の人間の生活、暮らし、文化を研究するものです。この現代版を考現学といいます。現在の人の暮らしや風俗を、観察・採集し、ありのまま記録し、研究するというもので、大正時代末期に、日本ではじまりました。この本「町のけんきゅう」は、わたしたちが一九七四〜九九年にかけて、日本各地の町や村を歩いて見つけた考現学採集をもとにして、本にしました。小学生から。
[日販商品データベースより]現在の人の暮らしや風俗を観察、採集し、ありのままを記録するのが考現学の方法です。カレーライスは店によってどんなかけ方をするか、おばあさんはどんなはきものをはいているか、ハンバーグ定食はどんな順序で食べるか、お風呂屋さんに来る男の人はどんな下着をはいているかなど、そういった町の考現学研究の第一人者が27年間の成果を絵本にまとめました。町歩きが楽しくなり、夏休みの自由研究のテーマ探しにも格好の1冊。
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 最強!カレー道 10歳から学べる食の本質
-
価格:1,760円(本体1,600円+税)
【2023年06月発売】



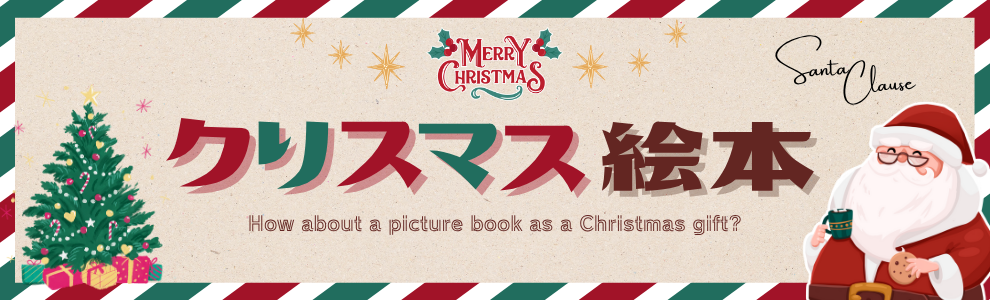










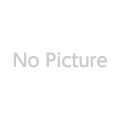

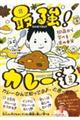






お薦めされていたので読んでみました。
ちょっと内容も古く今はほとんど見ないものもあるのですが
子どもたちも興味を持ってじっくり見ていました。
調べていることも特別なことではないので、
気軽に始められるし、
なにより普段見慣れている町が
違うように生き生きして見えそうです。
おそらく、子どもたちの町や人の見方も
少しは変わるのではないでしょうか。(まことあつさん 30代・東京都 男の子7歳、男の子4歳)
【情報提供・絵本ナビ】