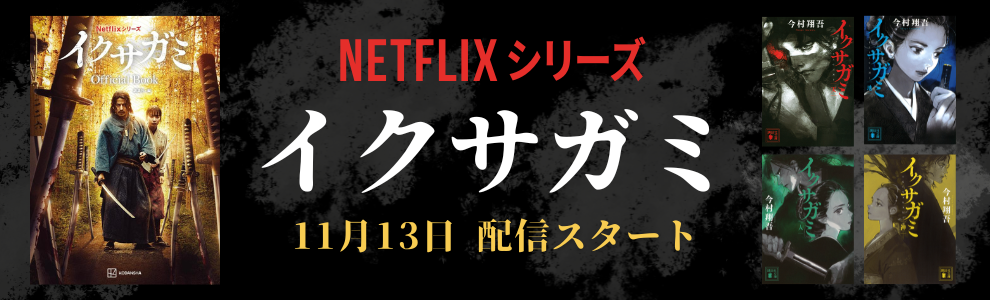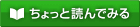[BOOKデータベースより]
和歌をめぐる学的営為の実態。歌学とは和歌という文芸を対象とする学問である。本書では、歌学において創出された知識全般を「歌学知」と呼ぶ。その具体相を探るため、種々の歌学書を調査・読解し、さらには説話文学・仏教文学・思想史学・書誌学といった周辺諸学にも目を配る。どの時代にどのような「歌学知」が、如何なる意識のもとに生み出されたのか、またどのような意識で利用され、変容していったのか―。動態を明らかにする。
第1部 初期御子左家の歌学(藤原定家における三代集注釈の位相―『僻案抄』を中心に;藤原俊成・定家の『奥義抄』認識)
第2部 鎌倉後期成立の歌学秘伝書(歌学秘伝書諸本研究の課題―『悦目抄』広本と略本の関係を例として;『和歌無底抄』諸本の考察;秘伝的歌学知と歌学書の創出・伝授―『和歌古今潅頂巻』『悦目抄』を中心に)
第3部 南北朝期歌学書『或秘書之抄出』考―秘伝的歌学知の展開一斑(南北朝期武家歌人京極高秀とその歌学;『或秘書之抄出』伝本考;歌学知の再生産―『或秘書之抄出』の生成と享受)
第4部 室町期冷泉流の『古今集』注釈(『古今持為注』の資料的性格―真偽の問題を中心に;三康文化研究所附属三康図書館蔵『為和秘抄』所収古今注をめぐって;上冷泉為広の『古今集』研究に関する一資料―広島大学蔵伝上冷泉為和筆(江戸前期)写『古今聞書』所収「後来迎院御注分」;『古今和歌集聞書(冷泉流)』という注釈書について)
第5部 説話と歌学知(歌学知としての説話―行基婆羅門和歌贈答説話の変容;金源三和歌説話と歌学知―「わがひのもと」という詞をめぐって;身分と表現の問題をめぐる中世歌学史―歌学書・歌合判詞の言説から)
和歌をめぐる学的営為の実態
歌学とは和歌という文芸を対象とする学問である。
本書では、歌学において創出された知識全般を「歌学知」と呼ぶ。
聖典とする『古今集』に関する注説はじめ、難義語の注釈、歌会作法、和歌の詠み方、勅撰集の撰集故実、和歌史の知識、歌人に纏わる説話、審美的歌論など、様々な内容の知が「歌学知」として捉えられる。
その具体相を探るため、種々の歌学書を調査・読解し、さらには説話文学・仏教文学・思想史学・書誌学といった周辺諸学にも目を配る。
どの時代にどのような「歌学知」が、如何なる意識のもとに生み出されたのか、またどのような意識で利用され、変容していったのか〓〓
動態を明らかにする。