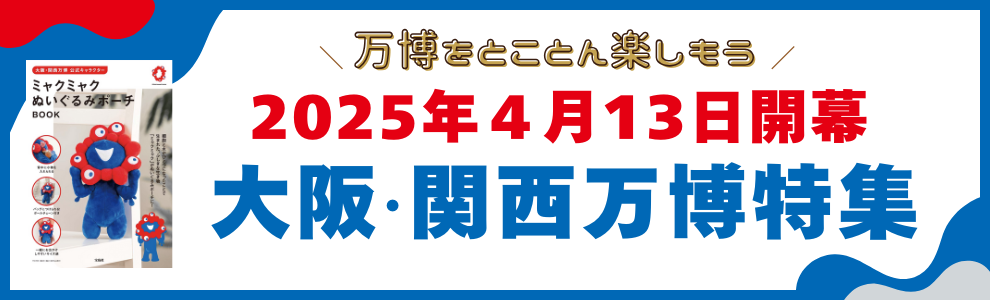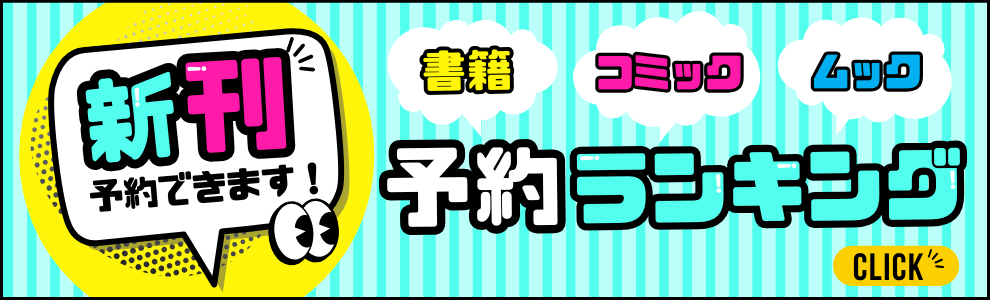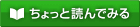[BOOKデータベースより]
学問が役に立つとは、学者のありかたとは、文学部で過ごした日々、研究のおもしろさ、元国語科教科書調査官の著者が折々につづったエッセイ集。
第1部 むなしい学問なのか(虚学の論理;ノーベル賞と旧石器;「勇気をもて。学者の良心を忘れたのか」 ほか)
第2部 文学青年から文学研究者へ(文学部への道;文芸部部室と無邪気な夢;中野三敏先生と和本修業 ほか)
第3部 国文学ひとりごと(作者は本当のことを書かない;二人のタケウチ氏をめぐる因縁譚;資料を読み解く面白さ ほか)
学問は即効薬ではない。即効薬ではないが、それなくして即効薬はつくれない。
学問が役に立つとはどういうことか。学者のあり方とは。研究のおもしろさとは何か。元国語科教科書調査官の著者がつづったエッセイ集。「第1部 むなしい学問なのか」「第2部 文学青年から文学研究者へ」「第3部 国文学ひとりごと」でつたえる、学問のススメ。
【学問には、その成果が見えるようになるまでに長い時間を要する分野がある。そのような長い時間がたつと、成果が見えるようになっても、社会と学問との接点はどうしても見えづらい。当の研究者でさえ、往々にしてその接点を捜しあぐねている。しかし、繰り返して言うが、学問は即効薬ではない。即効薬ではないが、それなくして即効薬はつくれない。
成果結果のあらわれるまでに長い時間を要し、社会との接点が理解されにくい学問、それが「虚学」であり、文学部はその「虚学」の巣窟である。】…本書「虚学の論理」より