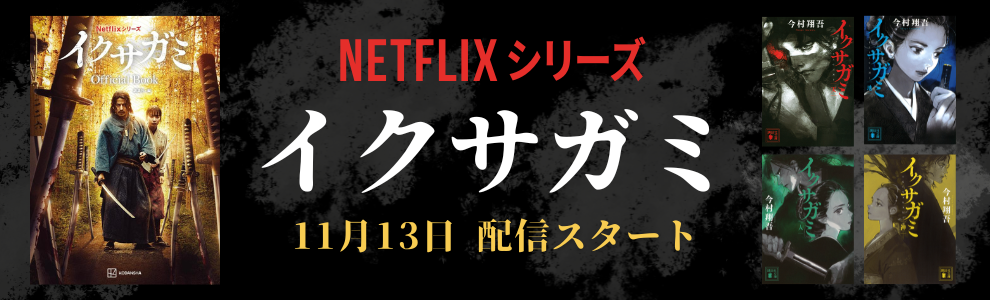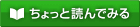[BOOKデータベースより]
四季に恵まれた日本では、古くからある年中行事に必ず特定の植物が登場する。植物の特性と広い歴史的見地を照らし合わせながら、行事の原点を解き明かす。そこにあるのは、縄文や万葉の時代から自然を愛し、時に畏怖し、自然と共存してきたかつての日本人の姿であった。
神と交わる木、マツ
アズキの威力
春の七草の変遷
節分植物を推理する
ウメの香
ツバキ五千年
ひな祭りの背景
花祭りの底流
花見の源流
フジの象徴と実用端午の植物
縁起と忌みに使われるウツギ
ユリの伝統
七夕に神のタケ
アサガオとホオズキの市
多目的作物ヒョウタン
盆の花
秋の七草考
ススキの系譜
サトイモは基層植物
モミジとカエデの国
キクの行事
クリスマス植物の由来
化身の花スイセン
正月の門松、雛祭りのモモなど、日本の行事やならわしには、決まった植物が登場する。それはなぜか。植物の特性と歴史的見地から、行事の原点を解き明かす。すると、自然との結びつきを大事にしてきたかつての日本人の暮らしが見えてくる。