- 江戸の本屋と本づくり
-
〈続〉和本入門
平凡社ライブラリー 747
- 価格
- 1,540円(本体1,400円+税)
- 発行年月
- 2011年10月
- 判型
- 文庫
- ISBN
- 9784582767476
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- そこにあった江戸
-
価格:4,950円(本体4,500円+税)
【2018年11月発売】
- キリシタン伝説百話 新版
-
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2012年04月発売】
- 幕末政治家
-
価格:1,111円(本体1,010円+税)
【2003年11月発売】
- 幕末明治大地図帳
-
価格:49,500円(本体45,000円+税)
【2021年02月発売】


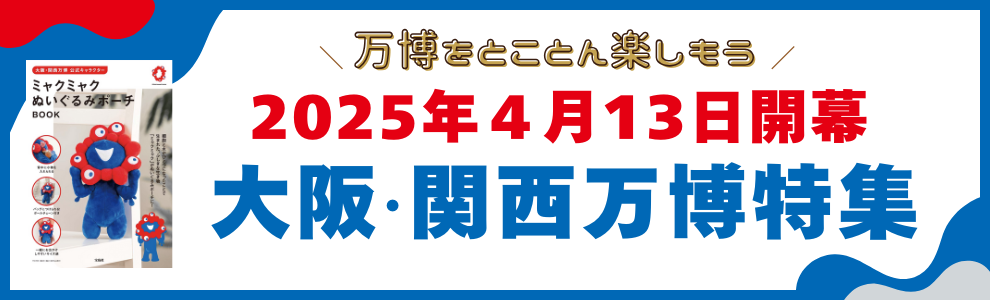
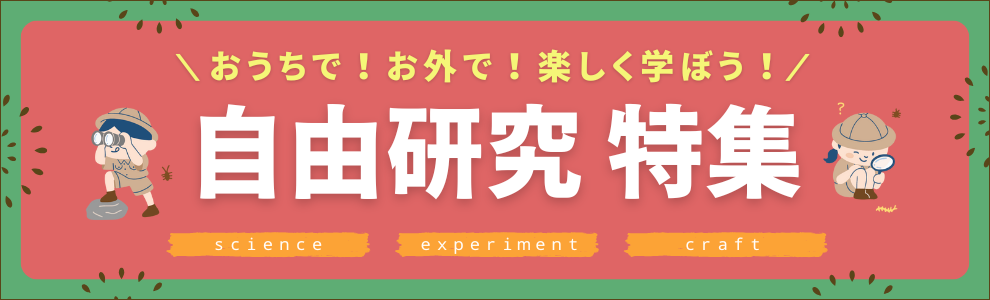






















[BOOKデータベースより]
現代日本の書物のルーツは和本にある。いま手にする和本の多くは江戸時代につくられた。京都・大坂・江戸では、大衆文化の興隆により、驚くほど多くの本が生み出され、流通していった。和本の持つ魅力が日本人の書物観を形づくったのである。江戸の本づくりと流通の仕組みを明らかにし、ますます面白くなる和本の世界がここにある。
第1章 和本はめぐる―復元、江戸の古本屋
[日販商品データベースより]第2章 本を「つくる」心情―私家版の世界から
第3章 本ができるまで―原価の秘密にせまる
第4章 本屋は仲間で売る―本を広めた原動力
第5章 写本も売り物だった―手書きでも大きな影響力
第6章 書物は読者が育てる―本を読むことの意味
補章 統計で見る江戸時代の和本―書物はどう広がったのか
書物好きの日本人はどのように形成されたか。多量に本がつくられ売買された京都・江戸の本づくりの様子から、和本を通して日本人の書物観を探る。好評の『和本入門』続編。